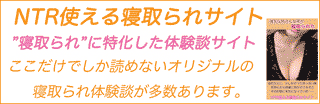週末の名古屋は熱い。
元々外食文化が盛んな街だけど、金曜日は特に仕事帰りの会社員から学生まで、東海一円から人が集まって、その中心である栄の熱気は深夜12時を回った頃、ピークに達する。
そんなありふれたいつもと同じようなとある金曜日、僕は久しぶりに会った大学の仲間とすでに3軒はしごして、広小路から少し南に入ったところにあるバーに行き着いた。
27歳前後になった僕たちはぼちぼち仕事でも責任ある立場を任されたり後輩の指導に当たるなどちょっとずつ大人へのステップを登り始めていて、こうやって学生時代のノリで飲んではいてもたまに真剣に仕事の話が挟まったり中には結婚しようと考えているやつなんかもいて。
変わらない仲間たちに流れる確かな時間の経過と成長がこそばゆいような誇らしいような、そんな心地よい夜を過ごしていた。
その店は雑居ビルの2階にある、ダーツとビリヤードが置いてあって、奥まった一角はダンス用のスペースがあるようなちょっと広だけどごく普通のありふれたバーだ。
雑居ビルの中とはいえ2面がガラス張の角に位置していたため閉塞感はなく、ネオンで照らされた繁華街の交差点を終電に遅れまいと足早に歩く女性や、なんとか今夜を一緒に過ごすパートナーを探そうと見境なく声をかけまくるナンパ男(いずれもビルの二階から見下ろした僕にはそう見えただけだけどそう外れてもいないだろう)の姿を観察できるような場所だった。
男ばかり13人というちょっとした大所帯で始まった今夜の集まりも、3軒目を終えた時点で終電で帰る奴もいて今は4人だ。
それぞれカウンターでドリンクを頼んで思いおもいにさり気なく同年代から上くらいの客で溢れる店内を見回している。男が飲み始めれば考えることは街角で必死に声を掛けている男とさ程変わらないんだろう。
僕も頼んだハイネケンの緑のボトルのネック部分を掴みながらざっと一回り店内を廻ってみた。
「今日結構入ってんじゃね?カワイイコ多いじゃん」
「つーかさ、この店も年齢層上がったよなー、昔は学生ばっかのイメージだったのに」
「そりゃ俺らが学生の頃から通ってるかなら、言ってみりゃ俺らと同じくらいの世代の奴らがそのまま持ち上がって通ってるってことっしょ」
「僕らも年をとったってことだよね」
「スーツ着てまでここに来るとは、昔は夢にも思わなかったけどな」
「いいんじゃない、スーツ、澤っち学生の時私服で来てたのよりモテるかもよ」
「スーツがモテるならアツシわざわざ家帰って着替えて来てんじゃねーよ」
「ほら、スーツだと踊りにくいからさ」
一時置いて窓際のテーブルに再集結した僕たちは与太話をしながらチューブトップで揺れる谷間や短すぎるスカートから伸びる太ももなんかを眺めながらひとしきり、久しぶりに入ったこの店についての雑感を語り合った。
確かに今日のお店は混んでいて、2台あるビリヤード台も3台あるダーツも人だかりができているし、15畳間ほどの広さがあるダンススペースでは、外国人を含めた30人ほどが音楽に合わせておしくらまんじゅうをするようにゴミゴミと蠢いていた。
「ちょい俺フロア行ってくるわ」
そう言っておしくらまんじゅうに参加しに行ったのはヒロシだ。今はローカルTV局の敏腕営業マンであるヒロシは昔からその本質が狩猟系で、学生時代から見事なアプローチ・商談・クロージング能力をもっており、東海一円の女子大生、時には女子高生も年上のお姉さまとも合コンを繰り返しては自分巣へと持ち帰り、またあらゆるクラブやバーで狩りの実績を積んできた猛者だ。
「クライアントをナンパしないように気をつけなよ」
と少しばかりの皮肉を込めてその背中に声をかける。とは言えヒロシが友達ごとごっそり女の子を連れてきたことも多々有り、僕達はいつもその恩恵に預かってきのでこの夜もそんな展開を期待していないというわけではなかった。
「ヒロシはほんっと変わんねぇな、少しは落ち着けってんだよ」友人の昔からの姿に少しばかりのノスタルジーを含んだ笑顔を浮かべてタカノリが言った。
「お前だって大して変わんないだろ。明日奈ちゃんに合コン行った事がバレて大目玉食ったお前が言えるセリフじゃねぇよ、なぁ、アツシ」その合コンに誘ってもらえなかったことで先ほどのお店で延々タカノリを非難し続けた澤っちが急に僕に同意を求めてきた。
「そうだね、確かにタカノリこそ落ち着きが必要だね、これで婚約破棄にでもなったら俺らだって寂しいじゃん」僕はそう言って学生時代から付き合い続けてようやく結婚を決めたタカノリの婚約者、明日奈の顔を思い出す。タカノリは明日奈の怒りを思い出して終電を逃した旨を言い訳でもするのだろう、慌ててスマホを操作し始めた。
そんな昔に戻ったような懐かしい会話に興じながらもやっぱり女の子の姿を目で追う。ヒロシはすでにおしりが見えちゃうんじゃないかというほど短くカットされたホットパンツにおヘソが見える丈のインナー、小さめのシャツをボタンを止めずに羽織り、ヘソを隠さないようシャツの裾を縛った格好で踊っている女性と向きあい、手をすでに女の子の素肌が露出した腰に回して一緒にステップを踏んでいた。
「さすがだね、ヒロシ。仕事が早いわ」さすがにここまで手際がいいと呆れてしまうといった風に澤っちが笑う。
「ほんと、僕にもあの積極性がほしいよ」
女性に縁がないわけではなかったけど前の彼女と別れて以来、合コンや飲み会で知りあう子はいてもどうしても付き合うまで踏み込めず何度かのデートや時には夜を過ごすことがあっても結局実りなくという生活を僕はもう2年も送っていた。
「空いたみたいだぜ、一勝負どうよ」必死にメールを打つタカノリを横目に、誰もプレーしている人がいなくなった一台のビリヤード台に目を向けて澤っちが言った。
「オッケィ、澤っち少しは上手くなった?」
二人は立ち上がりビリヤード台に向かう。
「もともとお前に勝てるとは思ってねーよ、チョー久しぶりだし」
「でしょ、ならせっかくだからドリンク賭けようよ」
「ぜってーやだ!」
頑なに賭けビリヤードを拒む澤っちは小学校からやっているサッカーを会社勤めの傍ら未だに続けているスポーツマンのくせに、ダーツだとかビリヤードだとか細かなことが苦手らしく長い付き合いになるが未だに僕に勝てたことはない。
バンキングすることなく澤っちが丁寧にナインボールのカタチを作る。ひし形にギュッと寄せられたボールを見て満足そうに頷くと白い手球を持ってブレイクショットの位置にセットする。他はともかくブレイクショットをキレイに決めるのが得意な澤っちからプレーを始めることはいつの間にか作られた暗黙の了解だ。
『パカンッ!』と大きく乾いた音につづいてカツンガツン、ゴロゴロ、ゴトンと耳障りの良い音が響く。3つほどポケットに収まったようだ。
迫力ある音に周りの視線が僕達のプールテーブルに注ぐのを感じる。
「相変わらず派手だね」
「パワーなら負けねーんだけどな」
「これで一度もブレークエースされたことないってのが信じられないよ」
と言いながらブレイクショットで落した澤っちが手球を2番に当てようと狙いをつけるが大きく的を外してファールとなり僕の順番が回ってきた。
「あーっ、クソ!やっぱアツシには敵わん」
あっという間にひとゲーム終えると自らキューをギャラリーの一人に渡してドリンクを買いに行く。
「逆にあのショットで勝とうとするほうが無理だよ」
5番まで落としてファールした僕の次、手球を慎重にセットしてポケット付近に在った6番を狙った、正直サービスショットを澤っちはかすりもせずに外してファールに。残り全てを僕に落とされるというまぁほぼいつもの展開だった。
澤っちの背中に僕は自分のジン・ライムのオーダを投げかけ、彼はそれに右手を上げて振り返らずに答えた。
その女性に声かけられたのはそんなやりとりをしている時だった。
「すごい上手だね、ひとゲームどう?ってか教えてよ」
背後から声を掛けられて振り返る。そこにはアラサーな女性がキューの先端にチョークをクリクリと押し付けながら立っていた。身長174cmの僕と殆ど変わらない目線の高さ、ちらっと見えた、さっき隣の台で連れの女性とキャーキャーゲームをしていたひとだ。落ち着いたブルーの花柄ワンピース、シックなんだけどノースリーブだしデコルテはざっくり開いているしひざ上はものすごく短い。肩までのボブも含めてなんとも露出だらけの服装だ。細い腕と胸元の大きな盛り上がりのコントラストに視線が集中しないように気を使う。
「教えられるほど上手じゃないよ、でもぜひぜひ、ご一緒させて」
一瞬敬語を使うべきか迷ったけど、あえて普通に話した。そうしておけば後で『失礼してスミマセン、でも全然年上に見えませんでした』と言うことができるし、それを聞いて嫌な顔をする女性は皆無だ。ということをヒロシから数年前に教わっている。
「ブレイク、苦手だから任せてもいい?」
「もちろんいいけど、そのまま終わっちゃうこともあるよ」
「そこはほら、手加減してね」
少し上から目線な、なんとなく命令に近いようなお願いをされるが悪い気はしない。
『カコンッ!』と音を響かせてボールが散らばっていく。落ちたのは2番の一つだけのようだ。
続いて1番、3番を落したところでファール、彼女の番だ。
ゆっくりと上半身をかがめる、ただでさえ開いてる胸元がつくる深い谷間がさらにあらわになって吸い込まれてしまいそうだ。短いスカート丈、後ろから見る男達の視線が露骨に集まるのが見て取れる。これ、ほとんど下着が見えてしまいそうなくらいせり上がってるんじゃないだろうか、なんてことが人ごとながら心配になる。
そのコはブリッジを作るためにすっと左手を台に載せる、キューがその上にセットされ…、あれ。
左手に違和感を感じる。その薬指にはシルバーにひかるシンプルな指輪がはめられていた。
『なんだ、既婚者かぁ』心の落胆を顔に出さないよう努めてショットの行方を見守る、キレイなフォームだけどどうしても左手の指輪と谷間に意識が持っていかれる。
彼女は3つ落として俺の番、7,8,9を無難に落としてゲームは終了した。
「ほらー、やっぱり上手」彼女は軽くあえてわざとらしく不貞腐れたような演技をしながら口角を上げて微笑む。
「俺なんて高校生の頃から11年、一回も勝ったことないんすよー」
いつの間にか戻った澤っちが僕にグラスを渡しながらしっかり敬語で話しかけた。
「彼女も上手だったよ、澤っちきっと勝てないよ、ね」
「確かに、さっき見てたけどあなたには勝てそうだよ」悪戯っぽく彼女は笑う。
「ほら、澤っち、彼女にもドリンク買ってきて」そう言って追い払う、彼女はさも当然かのようにスプリッツァーを彼に申し付けた。
「澤っちはわかったけど、お名前は?私はユミ」そういえば自己紹介すらまだだった。
「アツシだよ、ユミって呼んでもいいのかな?よろしくね」
「全然呼び捨てオッケーだよ、アツシも大丈夫?」
「うん、もちろん、あ、よかったらどっか座る?」
グラスの赤ワインらしきものを飲んでる彼女の連れのユミと負けず劣らず露出が高く、しかも高身長な女性と一緒にタカノリが未だスマホとにらめっこしている席へと向かう。
こちらを見て一瞬驚いたような表情を見せてすぐに平静を取り戻すタカノリ。
「アツシ両手に華かよー。気をつけてね、こいつこんな人畜無害そうな顔しててケッコー手が早いから」僕は呆れたような苦笑いを彼女たちに向けて肩をすくめてみせる。
「アツシ軽い男だったんだ、そんなふうに見えなかった、ショックー」ユミはさほどショックを受けていなそうな顔でケタケタと笑い声を上げて僕をからかう。
「そりゃあ僕にだって人並みに女性好きな面あるけどさー」僕もたじろぐふりをわざとらしく作って話にのっかる。
ドリンクを持って戻った澤っちを含めて5人で改めて乾杯、自己紹介する。タカノリも婚約者たる明日奈との間にあったであろう厄介事は吹っ切れたのか諦めたのかスマホから目を離して楽しそうにはしゃいでいる。女性がいるとテンションが明らかに変わるのも学生時代から変わらない。
盛り上がりを見せる5人、そのさなか年齢の話がでた。彼女たちは二人共29歳、学年で言うと2つ上になる年齢だ。早速ヒロシ直伝の台詞を使う。
「ホントに?歳上なんだ、全然見えなかった、っていうか二人共年下って思ってた。ごめんね、なんかフツーにタメ語で喋っちゃってて」
そのセリフを聞いた二人の反応は明らかに好意的なもので、僕の肩を二人でペシペシ叩きながら「えー、うそー、もう全然若くない。おばさんだよぉ」だとか「あ、でも割りと童顔に見られるんだよねー」といった謙遜を混ぜつつも喜びを全身で表現してみせていた。ヒロシ、恐るべしだ。
「ふとダンスフロアを見るとヒロシはすでに先ほどの女性と隅の暗がりでキツく密着して踊っている。
「あーあ、ヒロシもうこっち戻ってこないんじゃない?」タカノリは少し羨ましそうに言った。
「しょうがないよ、ヒロシだもん。僕たちは僕達で楽しく飲も」視線がフロアに集まったのを感じもう一度話の輪を戻そうとして僕は言った。けどユミが意外とフロアに食いついた。
「そういえば私、今日まだ一回もフロア行ってない!アツシ一緒に行こうよ」
そう言い終わる前にユミは椅子を立ち僕の腕を掴んでいた。目の高さに揺れるワンピースの裾とホッソリと伸びた脚に一瞬目を奪われる。
『ヒューゥ』という古臭くてわざとらしい口元と表情だけ作って澤っちがニヤけながら僕と目を合わせる。少し照れた僕はやれやれといった苦笑いに似た表情を心とは裏腹に残る二人の男友達とその二人に挟まれて「いってらっしゃーい」と手を振るユミの友人に見せて席をたった。
ユミは僕がすっかり立ち上がるのを待たずにしっかり腕を回して俺に寄り添いフロアへと半ば引っ張るような勢いで歩く。左腕に柔らかな胸が押し付けられその弾力を感じとろうと全身の神経が僕自身の意志とは関係なく集中しているように感じる。ただし目線は僕の手の甲に添えられた左手薬指の指輪を捉えた。年齢の話はしてもなぜか男友達は二人とも指輪には一切触れていなかった。
フロアスペースは踊るというより軽くステップを踏んで身体を揺する程度の隙間もないほどごった返していた。遠くからは確認できたヒロシの姿は人混みに入ってしまった今となってはもう見えない。
ユミは僕の正面に回りこんで、胸元を押し付けるように僕に密着して巨大なスピーカーから流れるダンスクラシックスの音量に負けないよう耳元で大声を出した。
「人、凄いね、ちゃんとはぐれないようにね」そう言って僕の背中にしっかりと手のひらを当ててぎゅっと抱き寄せる。
軽く口角を上げて微笑みだけ返し、僕もユミの腰元に手を置き少しだけ抱き寄せる。あちらこちらから奇声に似た歓声が頻繁に上がりむっとするような熱気に汗ばんでしまう。
胸を僕に押し付けたままユミは左右に身体を揺さぶる。腕にあたっていた時よりもさらに敏感にその柔らかさを感じた。平気なふりをしないと全身の毛穴から汗が吹き出てしまいそうだったのであえて指摘する。
「ユミ、胸大きいよね。すっごい柔らかいのさっきからあたってるんだけど」
「タカノリくんが言ったとおりだ、やっぱりアツシそんなことばっかり考えてるんだね」僕の反応を楽しむように顔を覗き込むユミのグロスがたっぷり塗られた唇が暗がりの中キラキラと光る。ここに唇で触れたらどんなに心地よい感触が得られるんだろう。
「そんなことってどんなこと?」努めて平静を装って聞き返す。ユミのペースに載せられるのも癪だ。
「そんなことはそんなこと、おっぱいとか、それにさっきからじっと私の唇見てるし」暗い中とはいえ女性は男の視線に敏感なものだ。
「ユミみたいな美人でスタイルいい女の子と一緒にいたら大抵の男は目線そらせないよ」
言い訳とも開き直りともつかないセリフにリップサービスも混ぜてお茶を濁した。
このセリフが思いのほか効果的だったのか笑顔の明るさが3段階ほど上がって僕を抱き寄せる腕の力が強くなる。
シュー、と音を立てて天井のパイプからスモークが吹き出す。夜中の濃い霧の中にいるように俄に二人の世界が作られる。ミラーボールとレーザーだけがその二人をその他の空間から隔絶する濃霧の壁にキラキラと光を映し出し時折飛んできた光にあたってユミの唇がつややかに揺れる。
僕らはどちらからともなく唇を重ねた。
強く押し当てた唇を離すとべとついたグロスが僕の唇に付着するのがわかる。そのまま2度、3度と唇を合わせる。音楽に合わせてステップを踏んでいた両足も今は申し訳程度に左右に揺らすだけだ。
ユミの腰に当てていた手をゆっくりと背中に移動させて少し強く擦るように抱き寄せ、今度は唇ではなくお互いのおでこを押し当てて見つめ合った。ゴテゴテと、ではなくしっかり一本一本がくっきりとした濃く長いまつげの奥にしっかりとこちらを上目に見据える大きな瞳が覗く。黒目がち、と言っても最近は黒目を大きく見せるためのカラーコンタクトなんて常識だけど、その大きさはどこか無垢さを感じさせる、もちろん出会って30分で抱き合い唇を重ねるこの状況に無垢も何も在ったものではない。
「唇、ピカピカ光ってるよ」意地悪っぽい笑みを浮かべてさっきまで自分の唇に押し当てられてグロスが着いた僕の唇を親指でなぞりながらいう。
「甘い匂いするんだね、これ」
それを聞いて今度は僕の首筋に唇を押し当てる。その部分の皮膚が、そのやわらかな感触とともにその透明でキラキラしたラメが入ったグロスが付着するのを感じる。
「首は思ったより目立たないね」ユミは少し不満気な声を漏らす。
「暗いしね、きっと明るいところで見たらくっきりなんじゃない?」
「みんなのところに戻ったら見つかっちゃうかもね」今度は嬉しそうにいう。コロコロと替わるユミの表情は見ていて飽きない。僕達の間で誰と誰がどうなろうとそんなことは慣れっこでワイシャツだろうが首筋だろうが股間だろうが口紅でもグロスでも歯形でもどうと言って騒ぎにはなりようがないんだけどそれを伝えるのはやめておいた。
「見つからないようにこのまま二人でよそ行っちゃおっか」僕はお返しとばかりになるべく挑発的な笑みを作ってまっすぐにユミの目を見つめる。想定していたケースは2つ、たじろぎや失望を一瞬(どんなに上手に隠そうとしても)浮かべてお茶を濁されるか、好色的な表情を見せてその提案を受け入れてくれるか。
どちらかと言うと後者、ただし表情は先程から浮かべているどこかイタズラっぽい微笑みを変えずにこの店をでてどこか別の場所で飲み直そうとユミは言った。
そうと決まれば、の早さでダンスフロアを離れると、とりあえず僕はみんなのところに戻り
「もう出るよ、おつかれさまっしたー」とだけ声をかけて店の外へと向かう、僕らの間では話はそれだけで済む。
ユミの連れの女性はいまだテーブルで僕の友人二人に挟まれて飲んでいるがユミからすでにメールをもらっているのか、もしくは察しが良いのか、意味ありげなほほ笑みだけ僕に向けて見送ってくれた。
「どこで飲もっか?」と尋ねる僕にユミは
「今日はタクシーで帰るの?」と早速僕に腕を絡ませながら返事をよこした。少なくとも終電はとっくに過ぎているし連れの女性とも別れた今、帰宅手段、もしくは電車が動き出すまでの時間をどう過ごすかは重要な問題だ。
いや、それよりもユミは左手の薬指に指輪をはめている。これを文字通り既婚者と捉えるなら始発以降まで過ごすというのも難しいんじゃないだろうか。
「うーん、考えてないや。僕の家上前津なんだ、だから歩こうと思えば歩けるし、何時まででもいけるよ」
今しがた僕達が飲んでいたのは名古屋の地下鉄栄駅と矢場駅の中間辺り、そして僕が住む上前津は矢場駅の隣の駅で徒歩にしても20分程度の距離だった。
「近っ!いいなー、羨ましい」心底羨ましそうな表情と声だ。
「ユミは、どのあたりに住んでるの」
「刈谷、めっちゃ遠いでしょ」
「そりゃ遠いね、って言ってもさっきのタカノリは岐阜だからね」
「岐阜も刈谷も時間的にはそんなに変わんないよ、県を越えないだけで」
「じゃあどのみち始発?」
「うん、タクシーじゃ帰れない」
「じゃあよかったら家で飲む?」
「え、いいの?いきたーい。てかさ、やっぱり手が早いんだね」にやけ顔を見せるユミのセリフをさらっと流す。
「えぇっと、たしかうちにお酒、ビールしかないけどなんか買ってく?」
「ううん、ビールがあれば十分だよ」
そんな話をしながら大津通まで出て、タイミングよく走ってきたタクシーを捕まえて乗り込んだ。
「近くまでなんですけど、すみません、大須の先にAOKIあるんですけど分かりますか、大須通を右折して。そこまでお願いします」
僕がそう言って手短に行き先を告げ終えると、ユミはさっきまで僕の左手に巻き付いていた腕を今度は右側からがっちり絡めて唇を重ねてきた。
お店では多少周りに気を使っていたのか、今回は舌で巧みに僕の唇をこじ開けてナメクジのようにヌラリと僕の方に侵入してきた。応じて舌を絡めると縦に横にと顔を動かしながらジュパッなんて音を立ててエロく僕の唇と舌にしゃぶりつく。あまりにも扇情的な音を立てるので運転手さんに申し訳なく思い、それとなく様子を伺うけど全く無反応に車を運転し続けていた。僕は右手をユミの頭に回して応じ、手持ち無沙汰の左手がユミの胸に伸びそうになるのを理性で押さえつける。
外の景色は見えていないけど体感で車が右折するのを感じる、もうまもなく停車するはずだ。
僕は一息つきながら唇を離す、ユミの瞳は名残惜しそうに僕の顔を見つめる。
にこやかに見送ってくれた運転手に車外から会釈して、ユミの腰を抱えるようにマンションのエントランスをくぐる。ユミは物珍しそうにキョロキョロしている。
「すごーい、なんか高級そうなマンションだね」
「たまたまね、親戚が海外行っちゃって管理の意味も含めて借りてんるんだ、ただみたいな金額で」
「へぇー、そういうラッキーってあるんだね」
ユミははじめて遊園地に連れてきてもらった子どものようにキラキラしためをアチラコチラに向けては楽しそうに笑顔を浮かべる。じっと横顔を見つめてみる。
ユミと出会ってからまだ50分程度だろうか、始めて明るい所でその顔を見たけど暗い所マジックがかかっていたわけではなく、本当に29歳にしては若々しい肌をしているし首筋も胸元も張りのある質感をもっている。
「まーた胸見てたでしょ」あたりをキョロキョロしていたはずのユミはいつの間にか僕の顔を覗きこんでニヤニヤしている。
「明るいところで見ても美人だし肌もつやつやしてて綺麗だなーって、思わず見とれちゃったよ」
顔色を変えずに正攻法、真正面から切り込んでみる。だけどユミも全くと動じる素振りを見せない。
「アツシ、ほんと見かけによらず女の子慣れしてるんだねー、お姉さん少しがっかりだよ」とあまりがっかりした表情は見せず言う、むしろさっきより口角を上げて嬉しそうにすら見えた。
そんな表情のままエレベータに乗り込むとすぐに正面から身体を寄せ、唇を重ねてくる。
僕だって女性経験が乏しいわけではないけどここまでイージーな展開は珍しい。指輪のことも有り一瞬美人局であるとかなにかしら罠的な危険も感じたけどまぁそんなトラブルは取るに足らない些細な事だ、据え膳を食べてしまってから善後策を考えればいいやと、目の間に置かれた幸運な状況を楽しむことにする。
停止したエレベータを待ちきれずにといった足取りで降りる。部屋までの距離がもどかしくも感じる。強くユミの腰を抱いて、ポケットからキーを取り出しながらそうとは気取られないようにゆっくりと見せかけた急ぎ足で部屋の前に向かう。ユミが右腕に押し付けるおっぱいの圧力も一段と高くなったような気がする。
ガチャリ、と扉が閉まるやいなや重なる唇。ユミの腕は今度は僕の首の後に回されている。靴を脱いでホールに上がりながらキツく押し付け合うようなキス。僕はユミの腰元に手をやるけど、そんなシチュエーションにさすがにそこが大きくなり始めていたので抱き寄せることを躊躇する。こんな状況でもまだそのことをユミに気づかれるのは恥ずかしい気がしていた。もちろんユミはそんなことお構いなしに首から背中から腰から僕の身体をまさぐるよに抱きしめ、シャツの裾から手を入れて素肌の感触を確かめるように手を滑らせる。
ここでバランスをとって置かないと二人のテンションに差ができてしまうかなぁ、案外冷静にそんなことを計算してユミのうなじあたりから背中まで伸びたワンピースのジッパーをゆっくり降ろした。当然だけど嫌がる素振りはない、というかそれを合図にするかのように僕のシャツのボタンに長いネイルで飾られた指を器用にかけて上から順に外し始める。
僕がすでに背後では腰元付近まで開いているワンピースの肩口を手前に引くと素直に手を前に垂らして脱がしやすようにしてくれる。腕から抜くとワンピースはストンとひっかかりもなく床に落ち同時にユミは僕からシャツを引き剥がした。
先ほどからずいぶんと僕や他の友人達の視線を集め続けてきた谷間がいよいよ露わになった。
飾り気のないシンプルなハーフカップで肩紐がついていないブラはその真っ白い大きな膨らみを支えるには幾分頼りなさげ見え、『よくこんな谷間、小さなフロントホック一つで支えられるよなぁ』なんて客観的な考えが浮かんでくる。
改めて腰に、と言うよりおしりを両手で鷲掴むように抱き寄せる、張りのあるすべすべとした質感がダイレクトに伝わってくるのはヒップラインを覆う布の面積がとても少ない、というかほとんど無いからだとすぐに気づいた。シャツを脱がせたユミはベルトの金具にとりかかってガチャガチャと金属音を立てている。僕は片手でおしりを弄りながらもう片方の手でブラのフロントホックをさぐる。ほぼワンタッチでホックははずれて、押さえつけられていた大きな胸の弾力で輪ゴムが切れたみたいにブラが弾け飛び、床におちた。
ブラの締め付けから開放されて喜ぶようにその迫力ある胸は存在感満点に僕の方に向けて突き出している。思わず手をのばすと、吸い付くような質感の肌がほとんど抵抗が感じられないほど柔らかに凹みをつくる。今度は持ち上げるようにして掌で覆うと、重量感と程よい弾力を感じた。
その感触を楽しんだのもつかの間、ユミは胸を弄ろうと意気込む僕の手を置き去りにしてすっとしゃがんでしまう。ユミはベルトは外し終えてジッパーを下げ、僕がユミのワンピースにしたようにストン、とはいかなかったけど、スリムタイプのパンツを足元もまで下し、僕が従順に脚を上げると足首からスルリと抜き取った。
ユミの目の前にはパンツを大きく盛り上がらせて(とは言え僕のは標準サイズだけど)、しかもすでに先っぽを湿らせているそれが存在を示威している。
そっとペニスの先に人差し指を当てるユミ。続いて掌で包み込むように優しく棹をなで上げる。
しゃがんだユミを上から見下ろすと、大きな胸とそれによって作られる深い谷間、しっかりとくびれたウエスト、そして大きく張り出したヒップラインなど幾つもの曲線を描いてシンプルに美しく感じる。
「先、もうヌルヌルしてきちゃってるよ」年上っぽい余裕たっぷりの笑みを浮かべてユミは僕を見上げて言う。改めて言われると若干の恥ずかしさを感じるけど、開き直ってこの場の雰囲気を盛り上げることに徹することにする。
「ユミみたいな美人さんのそんな姿見せられてこういう風にならない男がいたら疑いなくゲイか下半身に深刻な悩みを抱えていると見るべきだよ」
「そんなまどろっこしいいかたされたら褒められてる気しないんですけど」口調は批判めいているけど表情は全くの裏腹だ。
ユミは両手をパンツのゴムにかけて下ろそうとする。玄関先で全裸になるのは一瞬ためらいがあったけどユミはそんなことお構いなしだ。
はっ、とおもう。添えられた左の手にはやはりシンプルな指輪がはめられている、その光景は罪悪感よりも背徳感に伴う一層の興奮を呼び込んだ。すでに誰かのモノになっている女性と繰り広げられる行為…
玄関ですっかり全裸にされたまま仁王立ちしている僕のそこにユミはそっと唇をつける。
舌先を伸ばして、先端にプクリとたまった透明な粘液を舐めとるようにすくい、ゆっくり離れる舌先と僕の先端の割れ目の間につつぅーと糸がひく。
さらにもう一度近づいたユミの舌は僕の亀頭に沿って円を描くように一周ぺろりと舐める。ジンッとする快感が腰のあたりに響き無意識に腰をかがめるような姿勢になってしまった。
その反応を見たユミはさらに嬉しそうに僕の表情を伺い、唇をすぼめてゆっくりとペニスを口の中に収めた。生暖かくてヌルリとした感触が直に伝わってくる。しっかりと唾液を絡めながら、舌先を細かく動かして亀頭全体やカリの部分を柔らかく刺激する。
僕はユミの頭に手をおいて、撫でるように動かしながらまるで湯船に使ったおじさんのように大きく息を吐いた。
ユミは喉元までそれをくわえ込むとゆっくりと前後に頭を振り始めた。右手で僕の尻を掴みこんで固定している。
「ユミ、凄くきもちいいよ、ねぇ、手も使って」優しく諭すような口調で僕はお願いする。
ユミはくわえ込んだままちらりと目線を上げて、左手を僕のペニスに添える、指輪をはめたその手だ。左手の薬指に指輪をはめたまま顔を前後させるのに合わせて上手に包み込むように手をストロークさせる。ジュポ、ジュポっという音が玄関に響き、音とワンテンポ遅れてユミの大きな胸がふるんふるんと揺れている。
さきほどから続くジンとした快感は徐々に大きくなって膝曲げて座り込んでしまいそうになるのを必死で抑えていた。
たまらずに僕はユミの腕をとって優しく立つように促した。ユミはペニスから口を離して物足りなそうな顔を一瞬見せたけど、すぐに意図を察したのかすっと立ち上がった。
立ち上がるユミをくるりと回転させて手を壁につかせ、おしりをこちらに突き出すような姿勢を取らせた。壁につく手にはめられている指輪をちらりと確認する。Tバックでほとんど隠されていていないおしりの丸みはとてもキレイで張りがある。僕は屈みながらTバックのほとんど紐のように細くなっている部分を横にずらし、両手でおしりの肉を左右にかき分けた。
そこはすでにぐっしょりと湿っていて、赤く熱を帯びてた。
そっと舌を這わす。瞬間ほんの少しの酸味を感じたけどちょうど鼻先に当たるアナルと同様にほぼ無臭で舌で触れた途端溢れ出した粘液で少し舌が痺れたような感覚になる。
「はぁ、あああん」少し抑えられたくぐもった吐息のような嬌声がユミの口から漏れでる。その声は僕の舌先の動きに合わせて強くなったり弱くなったり断続的になったりする。声の変化を聞きたくて僕は夢中で吸い付くよに膣の入り口とその周りを覆う唇に舌と唇で刺激を与え続けた。僕の唾液とユミから溢れる粘液でそこはもうベトベトだ。
「はぁあ、ねぇ、もう、欲しいよ」吐息の合間を縫うようにとぎれとぎれにユミは言った。
スクっと立ち上がり壁に手をついたユミの脇の下から体に手を回して、両手のひらで握り潰すような強さで大きな胸を揉みしだくけどほとんど収まりきらない。先端の敏感な部分に触れる度にユミの体がビクンと震えるのがわかる。
首筋や肩甲骨の隆起やうっすら浮き出る背骨の凹凸の感触を舌で味わいながらひとしきり胸を掌で転がしたあと、Tバックをずらして普段より大きくなった気がする僕のペニスをヌルヌルとした入り口にあてがい、ゆっくりと焦らすように擦った。
「あぁあ、凄い、アツシ、熱いの当たってるよ」
そう言うとユミは自らの右手をガイドにして、僕のペニスがちょうどいい角度で当たるよに導く。僕の先端はユミの張りつめた敏感な部分に当たる。
「ああっ!ねぇ、当たってる、私のクリにこすれてるぅ」
腰を細かく揺すってみたり角度を変える度にユミは声の色を変えて反応する。
「ねぇ、ユミのせいで僕のドロドロになっちゃったよ、どうしよう、このまま入っちゃいそうだよ」
「あんっ、いいよ、このまま入れてぇ」
ユミは催促するように右手を使って僕のペニスの角度を変え、膣口にまっすぐ当たるように調整する。先端が吸い込まれるようにユミの中に入っていく。じっとりと熱くトロトロとした粘度の高い液が溢れたそこにどんどん埋まっていく。
「入れるよ、このまま、入れちゃうね」
耳たぶに軽く歯を立てながら息を吹きかけるように言葉をかけ、同時にさらにゆっくりとペニスをユミの体内に侵入させると奥へ奥へと誘いこむようにしっかりとユミの膣壁に捉えられる。
我慢できずに奥までズンと突き上げた。
「あぁああっ!」廊下に漏れ聞こえてしまいそうな大きな叫びをあげる。まるでバキュームで吸い上げるようにユミの膣はキツく僕のペニスを締めあげる。
「凄い、ユミの中、気持ちいいよ、熱くなってる」
勢い良く腰を打ち付けると肉付きの良いユミのおしりの肉が心地よいクッションになってくれる。
僕はTバックをずらしていた右手を離してユミの前に持って行ってそのままパンツの中に潜り込ませた。薄い陰毛をかき分けて僕のペニスが激しくストロークする割れ目の上ではちきれそうに膨張していたクリトリスを人差し指と中指を使って挟みこむようにこすった。
「ダメー!あぁあ、それ、イッちゃう!、あっ、ねぇ、キモチ良すぎるよぉ!」
一際大きな声をあげたユミの膝がガクガクと震えるのがわかる。それでも容赦せずに腰で思い切り深いところまで突き上げながらクリを攻め続けた。とどまることなく溢れ出るユミの白濁した粘液は僕の太ももまで伝い、生暖かく濡らす。
「ねぇ、ああぁ、ダメだよ、ねぇ、もう、イッちゃうよ!」
ユミの訴えを僕は平然と無視して腰を打ち付け、クリトリスを嬲った。
ジュパ、ジュパっと、溢れでた液体の音がどんどん増していく。そしてユミの体が細かく痙攣した。
「はぁあっ!ああぁあイクゥゥ!」
ユミは叫ぶとともに背中を大きく仰け反らせると、僕のペニスを引きちぎらんばかりに激しく膣を収縮させてイッてしまった。
壁に手をついたままハァハァと大きく肩を上下させるユミからペニスを引き抜いて、ふらふらする足元に気を使いながら手を引いて、リビングルームへと続く扉を開いた。
僕にさらに奥にあるベッドルームまで行く余裕はなかった。
すぐにユミをソファに仰向けに横たえると両腕でユミの脚を大きく開きもう一度ペニスをあてがった。
「ユミ、挿れるよ」
上気した顔に目を潤ませたユミは力なく二度頷くと、再び侵入した僕のペニスが与える刺激に体を震わせて声を上げる。
仰向けになったユミの胸はさすがに自身の重みに勝てないように少し偏平になっていたけど、それでも十分すぎるほどの盛り上がりを見せている。僕は両手でユミの手をとってそれぞれ掌を合わせる形につなぎ、腕で胸を挟みこむようにクロスさせて腰を突く度に大きく揺れる景色を楽しんだ。
絡ませる指にひかる指輪にやはり目が行き、言い難い優越感に似た感情が快感を高める。
「胸、凄いね、めっちゃ揺れてるよ」
「もっと、もっと突いて、おっぱいも、もっと舐めてぇ」甘くおねだりするユミの表情に先ほどまでのお姉さん的余裕はもう無くなっていた。
ユミの乳首を唇に含んだり深い谷間に顔をうずめてその柔らかさを感じたりする度にユミの声は高くなっていき、呼応するようにウネウネと締め上げるユミの膣の動きに徐々に僕の射精感も高まってくる。
「ユミ、ごめん、そろそろイキそうだよ。どこに出せばいい?」
「いいよ、はぁん、アツシの好きなところに出して」
「ゴムしてないのに、そんなこと言ったらこのまま中に出しちゃうよ」
「中に出したいの?」ここで少しだけ焦点が虚ろげだったユミの目にしっかりとした光が戻ってきたようだ。
「ユミこそ、中に欲しいの?」僕の中の天邪鬼が出したい、とは言わせなかった。
「中に、アツシが出したいなら、出しても、いいよ」少しだけイタズラっぽい笑みを作る。呼吸は荒く乱れていても少しだけ上から目線を復活させたのはお姉さんキャラの矜持だろうか。
「今日大丈夫な日なの?」
「わかんないけど、いいよ、大丈夫だから、そのまま、出して」その目は僕の反応を楽しもうと表情を探っているようだ。僕はこみ上げる射精感とその表情が作る誘惑にどうしても勝てない。