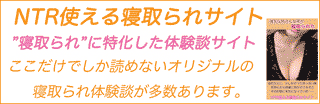28才最後の一日が、もうすぐ終わろうとしている。
ベットサイドで瞬く時計のデジタル表示に目をやったのもつかのま、ぬちっと腰を浮かせた若い彼がお尻の肉を鷲づかみにし、背後から深々とカラダを抉ってきた。
私のカラダを満たしていく、深く熱い実感。
重なり合う裸身がうねり汗ばみ、ほぐれてまた繋がりあう。
「ん、んはぁ‥‥ンンッ」
「ぐっっ‥‥」
わずかに開いたカーテンの向こう、夜景をバックにした窓ガラスに自分の顔が映りこむ。
形のいい眉を切なげにひそめ、紅く羞じらう唇はハァハァ荒い呼吸で半開きのまま。会社では決してみせない女の顔だ。私の、本当の顔だ‥‥
人をお局扱いして遠巻きにする後輩OLたちは、こんな姿をどう思うだろう。まして、彼女たちから人気の高い彼を、私がひそかに独占していると知ったら‥‥
「ん‥‥イィッ」
こりっと耳をかじられて、はしたなくハスキーな声があふれた。夜景に重なる彼の顔が小さく笑みを作り、満足げな仕草にキュウッとカラダの奥深くが疼いた。6才年下の彼を悦ばせている自負心と、火照った身体を煽られるいじらしさが、心をドロドロに溶かす。
感じてしまったことを彼に悟られるのがなぜか悔しい。
ぎゅっと唇をへの字に曲げていると、彼が2本の指を口内にさしこんできた。柔らかい指使いで鼻の下をくすぐり、吐息にまみれた半開きの唇をねぶりだす。
「愛してる」
耳もとの囁き。なんてツボを心得ているんだろう。年下のクセに。
いやらしい。
上と下と、両方から犯された私のカラダは、もう満足に返事も言えない。
「あっ、あフ‥‥」
下半身を貫くストロークにあわせて、入りこんだ彼の指が口腔を侵食してくる。舌先を指でつままれ、なまなましい衝撃でうなじが痙攣を繰り返した。窓に映る自分自身の瞳にやどるのは、ゆらゆらくすぶりつづける悦びの情炎だ。
「ひぅ、くぅんンンッ‥‥」
「‥‥」
ほとんど喘ぎ声を出さず息を吐くだけの彼と対照的に、私のカラダはびっしり汗に濡れ、たえまなく全身がよじれていくようだった。ハスキーにかすれる自分の呻きが恥ずかしく、いやらしい気分が波打って押し寄せてくる。
うつぶせの姿勢で押しつけられ、ひしゃげた乳房に彼が手を伸ばした。充血した柔肌を揉みしだかれ、私は思わず、ギュッとその手の上から指を絡めて押さえ込んでいた。敏感な反応を見てとって彼は薄く笑い、吐息を耳に吹きこむ。
「そんなに気持ちイイの? 年下に、いいように煽られるのが」
「ンッ‥‥」
彼の言葉責めは、燃え上がった私のカラダを心地よく愛撫する。優しく溶かすぬくもりとイジワルな台詞のサンドイッチで、はしたないほどアソコが反応してしまうのだ。
「はぅン!‥‥そ、そこっ、ダメ‥‥」
「ギャップが素敵だよね。けっこうマゾッ気あるし。彰子さんは」
ぬるる、パァァン‥‥ずぬぬッ‥‥パァァン!
本気の愛液をズクズクに混ぜ合わせ、シェイクして、クレヴァスのとば口から最奥まで長いストロークが何度となく繰りかえされる。熱いシャフトで強引に肉壁を拡げられる快感が私をすっかり馬鹿にさせ、獣のポーズをとらされた腰を引きずりまわすのだ。
「わっ、私は別に‥‥っひぃぃン、普通なのに‥‥っくぅ」
「説得力‥‥んっ、ないですよ‥‥」
「きひっ」
そう。分かってる。誰が見たって一目で分かる、惨めな証‥‥
ぐいっと手綱を引かれ、私はたまらず海老ぞりに反りかえった。つかんでいたシーツにさざなみができる。無意味に暴れる膝をつかんで、彼がわざと私の腰を高く掲げる。誇示するかのように、パァンパァンとクレヴァスの根元まで突きこんでくるのだ。
エアコンの風が強くなり、カーテンが大きくゆらめいた。鏡のように澄みきった窓に、もつれる2人の姿が映りこむ。
「ほら、見て‥‥会社の誰にもみせたくない、ボクだけの彰子さんだ‥‥」
「ふぅっ、ふぅぅぅっ」
ダメ、見ちゃダメ、私が私じゃなくなる‥‥
経験で知っているいるのはずなのに、そそのかされるまま視線が窓の方を向いていく。
暗い窓に映った、細い首筋を鮮やかに彩る恥ずかしい快楽の証へ。
ペットのように、しっかり繋がれた私自身に。
「エッチの時に首輪をつけてくれる女性なんて‥‥しかも本気で感じてくれる女性なんて‥‥彰子さんほど可愛い女性、どこにもいません」
「み、見ないでぇ‥‥」
吐息混じりに叫んでも、こみ上げる疼きをこらえきれない。しなやかに背筋にそらし、快感をかみ殺して蕩けている私自身の顔‥‥その喉もとには、彼に嵌めさせられた惨めな赤い犬の首輪が食い入っているのだから。
ゾクンゾクンと、体全体を被虐的なおののきが突き抜けていく。見せつけられる現実にカァァッと素肌が燃えあがる。
あまりにあさましく、エサをねだるように年下の彼氏の前で発情している自分に。
シーツに4つん這いになって爪を立て、首輪のリードを握られて自由自在にアクメまで追い上げられていく私自身の姿に。マゾのように、獣のようにアクメを貪りつづける私の、止まらないカラダの反応に。
「いっ、いやぁぁァ‥‥恥ずかしいぃぃ‥‥‥‥」
嫌がる言葉と裏腹に、トロトロに溶けきった語尾が尻上がりにめくれかえっていく。
ズブズブッと、強く肉洞をこすりながら彼自身を挿し込まれて、声を失った。下腹部が獲物を咀嚼する蛇のようにぎゅうっと蠢く。一つ一つ繊毛を収縮させる微細な肉感が巨大にうねり狂う快楽をこじり、私の中にドロドロそそぎこんでいく。
快感すら私の自由にならず、彼のペースで昂ぶらされていく。
気持ちいい。けれど、惨めだ。快楽でしつけられて、彼から離れられなくなっていく。
ズン、ズンと子宮の底に容赦ないストロークが叩き込まれていく。
「イク‥‥んっ、んんンンンン‥‥ッッッ!!」
吐息を重ねたシンフォニーが、いやらしく甘い音階を駆け上がっていく。
不本意にも私は彼を深々と噛みしめたまま、真っ白に弾けるまで追い上げられていった。
☆
目覚まし代わりのCDコンポが、お気に入りの洋楽をかなでだす。初登場チャート3位の、実力派女性ヴォーカルの新曲だ。
「ん‥‥んーっっ‥‥」
けだるい伸びをしたときには、ベットルームは燦々と冬日に照らされていた。白で統一され、こだわりぬいたインテリア。冗長なOL生活へのささやかな反抗がこもった自慢の1LDKだ。
エアコンの涼風が、毛布にくるまれた裸の肌を柔らかく包みこむ。
寝返りを打つと、隣のシーツのくぼみはまだ暖かい。乱れすぎた昨日の夜を思いだして顔が上気する。喉元をさぐると、赤い首輪は吸いつき、南京錠もかけられたままだった。
獣の証。マゾの証。快楽の、源泉。
小さくため息をつき、彼のことを‥‥彼の、特殊な性癖を思う。
彼、原口良平は今年入社したばかりの新入社員だ。目鼻立ちがぱっちりし、愛嬌のある可愛らしい男性だ。それでいて会話もうまい。おどけたり場を和ませつつ、自分のペースで周囲を魅了するしたたかさがある。新卒の23才。あらためて言うまでもないが、私とは6つも年が離れている。
職場で知り合った当初、彼と男女の仲になるなんて想像さえしなかった。
素敵な男の子だとは思ったけど、同期や1つ2つ上には彼を意識する後輩OLがたくさんいた。悔しいけど彼女たちは若さで輝いている。肌のハリもいいし、会社の制服だってよく似合う。余暇の過ごし方もずっと華やかだ。
私だって昔は‥‥そう思う記憶のなんと遠いことか。
いくつかの恋を重ね、逡巡し、気づいたら私がお局と呼ばれていた。所詮、OLなんて使い捨て。能力より何より、職場を華やかにさせる空気が大事らしい。言葉に出さずとも、そうした気分は会社というシステムのすみずみに行き渡っている。
22,3才のOLが大手をふる社内では、29才の女性など色眼鏡でしか見てはもらえない。
刺激のない毎日が、ゆっくり自分を錆びつかせていく。
そんな時、私は良平から口説かれたのだった。
驚きと、忘れていた喜び。
良平は、私を一人の女性に戻してくれる。いとおしく思われ、大切に扱われる甘やかさ。
恋という名のみずみずしい悦びがどれほど日常をうるおすものか。ひさしぶりの甘い果実を、私はわれを忘れて貪っていた。
そして私は、人知らぬ彼の性癖を肌で覚えることになったのだ。
「あ、起きたかい、彰子。おはよう」
「うん。おはよう、良平」
バスルームの音がやみ、ひょいと下着姿の良平が顔をのぞかせた。剃りかけの電気シェーバーを置いて私のところまでやってくる。頬をなでるように手で包み、そっと朝のキス。
良平は、こんなところまでマメで素敵だった。
とろんとしてばかりはいられない。うなじに吸いつく首輪を示し、訴えかける。
「良平、そろそろ外して」
「あ、ゴメン」
セックスの時に首輪を嵌めてほしい‥‥初めてそうねだられた時、目が点になった。
SMプレイ‥‥らしいが、私にはまったく理解できなかった。恥ずかしいし、それ以上に惨めだ。本気で怒った私を良平は必死で説き伏せ、一度だけだからと年下の甘えで上手に媚びた。
そうして‥‥
首輪でつながれた時、私のカラダは私のものでなくなった。
怒涛のような快楽と疼きの波濤に押し上げられ、肌という肌のすべてが剥きだしの性感帯になったようだった。何度も狂い、カラダが跳ね、それでも収まらずに痙攣しつづける。
やっぱりだ、と彼は言った。彰子さん、マゾですよ、きっと。
そんなのあんまりだ、と思う。けれど屈辱的な行為と裏腹に、ケモノ扱いされる私の躯は悦び、あさましく惨めにのたうち、打ち震えたのだった。
「んッッ」
カチリと音をたてて、喉もとに吸いついていた皮の感触がはがれる。物足りないような、ほっとしたような感情に揺れる私を、良平が楽しそうに見つめていた。思わずうろたえる。
「ふふ、また今晩もしてあげますから。がっかりしないで」
洗面所に戻っていく年若い彼の裸の背を見ながら、私は複雑な心境だった。
日曜の朝遅い食事を恋人と済ませ、私は良平を送りだした。良平の方は親と同居だが、ここしばらくは半同棲のような生活が続いている。彼の姿が見えなくなると、統一されたインテリアが急にがらんと空虚な感じに変わってしまった。
さんさんと降り注ぐ冬日の中、しばしボーっと立ちつくす。時刻は、朝の9時すぎだ。
29才と1日目を迎えて最初の朝。もう、30のとば口まで来てしまった。
同期入社の多くはすでに寿退社か、やりがいを求め転職してしまっている。彼と過ごす時間はすべての難題をうやむやにする麻薬めいたひとときだが、一人に戻ればその反動も心におしよせてくる。さっきまで躯を抱擁してくれていた良平の感触がよみがえり、小さく息がもいれてしまう。
こぼれた吐息には、快楽のそれよりも、困惑とあきらめが色濃くいりまじっていた。
急に電話が鳴り、われに引き戻される。
「はい、中谷です」
「ああ。彰子かい? お誕生日おめでとうね」
ディスプレイの名前表示を確認もせず、あわてて受話器を手にした自分を、私は恨んだ。
昨日電話がなかったせいですっかり油断していた。ほかでもない、もっともおそれていたもの。母からの電話だ。
案の定、誕生日を祝う母からの言葉は名目で、本題は別にあった。
「‥‥その話は断ったじゃない」
「でもねぇ彰子。富子おばさんだってお前を心配してくれて色々お話を聞かせてくれるのだもの。私だって早く安心したいじゃないの」
はっと失言に気づいて母が息を飲む。それが、半端な共感がまたいっそう苛立たしい。
「こんな気持ちで会ったって、相手に悪いだけでしょう」
「それはお前、実際に会ってみないと分からないわ。母さんだってお見合いだったもの。
愛情なんてものはね、お金と生活さえあれば後からついてくるものよ」
もう幾度となく繰りかえされたやりとり。母の用件は毎度変わらぬお見合いの話だった。
「分かった、分かったから。考えるだけは考えるから」
「本当かい? じゃあさっそく富子おばさんに連絡しなきゃいけないわよね」
語尾の跳ねあがった母に、私は深々とため息をついて電話を切った。腹立たしさと憂鬱が入り交じっている。私が考えてないと、悩んでいないとでも思っているのだろうか。
一人きりの部屋を眺めて洩れたため息と同じもの、同じ憂鬱の原因。
『だれかお付き合いしている人はいないの?』
この母の問いに、私は黙るしかなかった。今はまだ良平を紹介することなんてできない。
経済力こそが結婚に不可欠な条件だと思っている両親に、6つも年下の彼の話などできるわけがない。まして彼を親に紹介するだなんて。
そもそも私自身が、良平が結婚について意識することを怖れていた。
私も良平もまた8ヶ月足らずだというのに。将来の話なんて、どちらもまだ口にさえしていないというのに。なのに、来年の今頃、クリスマスを迎える頃には、私は30の大台にのってしまうのだから。
親にも同僚にも言えず、まるで隠れるように彼とつきあわなければならない後ろめたさは意味もなく私の心を重くする。けれど私は、どうしてもそのことを口にはできなかった。
ほのめかすことさえ、怖くてできないのだ。
年上が好きだと言ってくれた。心を許せると言ってくれた。一途に私をくどいてくれた。
なら、もし私が親に会って欲しいと、婚約したいと、そう告げたなら‥‥良平はそれでも良平のままでいてくれるだろうか。今までの男性のように急に不機嫌になったり、縁遠くなってしまわないのだろうか。
私が内心焦っていると知ったら、良平はどう思うのだろう。そんな、つかのまの幸せと将来とを天秤にかけた打算的な思考に嫌気がさし、再び鳴った電話をとる手は乱暴だった。
「あらぁ、どうしたの、けんか腰で」
「あ‥‥なんだ、敦子(あつこ)じゃないの」
からかうような口調が流れだし、私は思わず頬をゆるめた。
「なんだはご挨拶ね、彰子。お誕生日おめでとう。それより今の声。彼と喧嘩でもしてる最中だった?」
「ううん、ちょっと別件。彼とは、今朝も一緒だったわ」
「あーらら、あけすけに。のろけ?」
「あはは」
佐々木敦子は、今も親しくしている数少ない同期入社の一人だ。前から弁護士への夢を捨て切れなかったという彼女は、OL3年目に突然、まわりが驚くほどあっさりと会社をやめ、資格予備校に通いながら弁護士事務所につとめだしていた。
目的もなくダラダラOLを続けてきた私にはない思いきりの良さを彼女は持っていて、さばさばした男性的な性格が魅力だった。
「お祝いをしたかったんだけど、どう? いきなりだけど今日のお昼とか空いている?」
「ええ、空いてるわ。久しぶりに会って食事でもしましょうか」
☆
値段もグレードも高めのランチを味わいながら窓の外に目を向ける。大通りの街灯には赤と緑の飾りつけがされ、街並全体が近づくクリスマスのムードを高めていた。
「あら珍しい。今年のは一人なんだ、敦子。ふぅ~ん」
「ちょっとなによー。聞き捨てならない台詞ね」
「ホントは山のようにいい男をストックしてあるんじゃないのー? 逆ハーレムみたいな」
敦子と私、二人してコロコロと笑う。
電話ではマメに連絡を取り合っていたものの、半年ぶりに会う彼女はさらに磨きのかかった知性派の美人になっていた。マニッシュなスーツをさらりと着崩す感じがおしゃれだ。
同い年なので、私も会社で見せない砕けた表情でくつろいでいられる。
「で、どうなの。彼氏は。何か悩んでいるんじゃないの」
「うん。まぁ、結婚のこととか、ほら年のこともあって考えちゃったりとか、ね」
かいつまんで話をする。
時折あいのてを入れて聞いていた彼女は不思議そうに首をひねった。
「そっか。でも、結婚の話は結局あなた自身が踏み切っていくしかないでしょうね。今のところラブラブで破綻要素もないし、パワーバランスで言えば彰子が上なんでしょう」
「うん。そうだ、ね」
彼の熱意におされ、付き合うことになって、たしかに追われる恋愛なのだから本来なら私が彼をリードするべきなのだろう。けれど‥‥と歯切れ悪く口ごもった私に、敦子の瞳の奥が光った。
「他にもあるんだね。悩みが」
やはり、親友の目はごまかせないらしい。
敦子のカンの良さに半分はホッとし、半分は困りつつ、まるで奇妙な腫れ物かなにかのように私はそろりと舌の先で台詞をころがした。
「‥‥その、彼の性癖のこと、なんだ」
口にしたティーカップを戻すほどの間、あっけにとられたまなざしが私をとらえていた。
「性癖って‥‥え、まさか。彰子の彼って‥‥」
言いかけた敦子は一瞬、表現を選ぶかのようにためらい、
「ヘンタイなんだ」
「‥‥‥‥わかんないよ、私には」
偽らざる本音だった。ストレートすぎる敦子の問いを、私は否定も肯定もできずにいた。
本当に、分からないのだ。なにが普通でなにがヘンタイなのか、その境界なんて。
SMについて知らないわけではない。
初めて彼とカラダを重ねたあの夜以来、私なりにその行為の意味について、そして何故自分がああも溺れてしまったのかを理由づけたくて、あれこれとネットで調べてはいた。
いわく、奴隷と主人。いわく、飼い主とペット。いわく、調教行為によって女をしつけ、男の望みどおりのカラダに仕上げていくこと。
いかにマゾ性を秘めた女を探しだすか。
そうやって口説き落とし、あるいは手なづけ、奴隷にしていくか。
そこに広がる言説の数々は、私を動揺させ、おののかせるに十分だった。
首輪をつけられての行為で乱れて狂ってしまう自分の性癖を知っただけで、本当の私は普通じゃないらしいということだけでも混乱するのに‥‥ネットにあまた転がるハウツーものは、決まってご主人様志望の男性にこう告げるのだ。
『SMの関係は愛情ではない』
『支配と服従の関係なのだと。信頼はあっても、愛ではない』
と。
なら‥‥本当の良平は、私のことを、どう見ているのだろうか‥‥‥‥?
☆
「なるほどねぇ。なんかディープな世界。一人で考えても堂々めぐりだよ、それ」
「うん」
「でも、普通に恋愛感情もあると思うよ、その子。じゃなきゃ、いくら彰子に隠れた素質
だか性癖だかあったって、同じ社に勤めているお局OL誘えないよ。手軽な女なんていう
にはリスク大きいんじゃん、なんかあった時」
さすがに敦子はのみこみが早かった。
私がもやもやしていた感情をきちんと言葉でまとめてくれる。結婚に焦ってるお局なら熱心にアタックすれば普通は嫌がることだってしてくれるんじゃないか‥‥本当は良平もネットで見かけたSMマニアと同じで、特殊なパートナーが欲しかっただけじゃないか‥‥そういう私の悩みを軽く一蹴してくれる。
「ネットのSM論なんて鵜呑みにする彰子が素直すぎ。誰が書いたかも分かんないのに」
「それは、そうだけどね」
でも、分からないのはいずれにせよ同じだ。首輪をつけてのセックスだなんてこれまで知らなかった行為なのだから。心と体がバラバラにほつれてしまうあの感覚がなんなのか、説明なんてつかないのだ。
別れ際、敦子はウィンクして囁いてくれた。
「あんただって私と同じくらい良い女なんだから、変なめげ方しないでよね。どうしても納得できないんなら、年上の女の魅力でリードしながら聞きだしなさいよ」
「それができれば悩んでないってば」
「できるよ、大丈夫」
軽くふくれっつらした私に笑いかけ、手を振って歩いていく。そんな佐々木敦子の後ろ姿は、でも、たしかにOL当時に比べれば年輪を経て、ぐっと魅力的に頼もしくみえるのだった。私もあんな風に成長しているのだろうかと、ふと自分をかえりみて思う。
「お帰り、彰子さん」
「え?」
靴脱ぎに並んだ彼の革靴に気づいて目をあげると、奥の部屋から良平が首をのぞかせて笑っていた。体調を崩しがちな母を気遣って、いつもなら日曜は実家に戻っているはず。
「あら‥‥ただいま。どうしたの、今日は」
「母さんの体調がよくてね。週末こそ彼女といてあげなさいって、諭されちゃったよ」
頭をかく格好がやけに初々しく、年相応にかわいらしかった。
わびしい部屋を彼が暖めておいてくれた。そう思うと無意識に顔がほころんでしまう。
自分の現金さにくすりと笑い、かかとをあげてヒールを脱いだ。唐突に良平が口を開く。
「きれいだ、彰子さん」
「なっ、ええっ‥‥なによ、藪から棒に」
「好きなんだ。彰子さんみたいにできる女性がそうやって靴を脱ぐ姿。すごく大人びてて」
「‥‥」
切り返しを思いつかず、子供のように頬が赤くなってしまう。
これが愛情じゃないなんてことがあるのだろうか。SMの奴隷を手に入れるための口実だなんてことがあるのだろうか。ネットで知識を得てから注意深く彼を見るようになっているけれど、セックスのその時をのぞいて、つねに彼の態度は柔らかく、私を包みこみ、甘えてきてくれている。
年下の若い彼氏を所有する喜び。
それは間違いなく、女としての自尊心をくすぐるものだ。
出迎えられ、立ち上がった彼の腕の中でキスを交わしながら思う。彼との関係を知って私は弱くなったのかもしれないと。どうしても、昼間、敦子に叱咤されたあのひとことを彼に問いただす勇気がないのだと。せめて誘導ぐらいはできるはずなのに。
のぞきこむ彼の瞳は、まるで疑いを知らない色に見える。私の方が汚れてるかのように。
「ねぇ」
「なんだい、彰子さん」
“私のこと、どんな風にお母さんに説明してるの?”
“6つも年上の彼女だなんて言うの、ちょっと恥ずかしかったりしない?”
そんなこと。
「ううん、なんでもない‥‥」
そんな風にカマをかけることさえ、今の私にはできなかった。彼を疑っているかのようで、信頼しきっていないようで、そして彼にそう思われるのが怖くてしかたない。疚しさにうつむきかけた頬を両手ではさまれ、掌の感触に全身がひくんとおののいた。
耳たぶをくすぐる男性の指先。頬がかぁっと熱くなる。
「どうしたの。悩みがあるなら俺に話してよ。相談にのれるかもしれない」
「ン、あ‥‥良平‥‥」
唇と唇が重なってはほつれ、吐息をこらえてしまう。ためらいがちな私を引き込もうと囁きの合間にちろちろした交合をしかけてくる。
「それとも、年下の男はふがいない?」
茶化した口調とうらはらの視線にドキッときた。
真摯でありながらどこか寂しがっているような、甘えつつも傷ついている。そんな瞳。
こんなにも、私は良平の思いを独占しているんだ‥‥
悩ましくも被虐的な、あの甘いひりつきが体の芯からこみあげてくる。カラダを重ねてしまえばいつものように悩みも困惑もすべてうやむやなまま押し流されてしまうだろう。
それは怖いことなのに、けれど彼に迫られれば拒めない。
敦子のアドバイスに従うなら今だった。
どうして首輪を嵌めるのか。どうして私を支配したがるのか。その一言が聞ければ‥‥
——本当に首輪のないセックスの方がいいの?
——そう、望んでいるの?
不意に頭をよぎった問いかけにひやりとした。本当に首輪を望んでいるのは、ベットの中での従属を望んでいるのは、私自身ではないのだろうか。初めて知ったエクスタシーの味。今までのセックスとは全然違う、奈落の底へ堕ちていくあの絶頂感。
「ん? ひょっとして‥‥?」
「あ‥‥違う‥‥」
目の前にさしだされた首輪の光沢に目を奪われ、どうしようもなく胸が昂ぶった。
今までにも幾度となく繰り返したのと同じ煩悶の果て、やはり今夜も認めざるを得ない。
パブロフの犬のように、首輪をされることで私は赤裸々な牝になってしまうのだ。欲しくてしかたなくて、けれど自分ではおねだりなんてできない。
愛しているからこそ、あんな獣のように乱れくるった姿は見られたくない。この矛盾。
「言って欲しいんだ、彰子。一度でいいから、君自身の口で」
「‥‥あ、イヤ」
良平は私を意地悪に試す。どうにかして私自身に言わせようと。こらえるカラダを熱く溶かして、ひたすらなキスが首筋から胸元へ、さらには鎖骨のくぼみにまで下りていく。
「恥ずかしいの‥‥本当に、ゴメンなさい‥‥」
「分かったよ。じゃあ、首輪をしても、いいよね?」
やはり、いつものように少しだけ寂しげな良平の言葉に、なぜか胸を締めあげられる。
コクンと頷く私は、ひりひりと火照った顔をそむけて、うなじをむきだしにさらしていた。
いつもと同じ行為。いつものように迫られて‥‥いつものように、歓楽を、噛みしめる。
今だけは、これで良い。そう思って流されていく。
☆
イブの晩が近づくにつれ、少しづつ私は落ち着きを失っていった。
良平とすごす初めてのクリスマス。次に聖なる夜をむかえる時、私はすでに30才なのだ。
このままズルズルと言いだせないままで良いのだろうか。結婚についてどう思っているか探りを入れたり、せめて首輪のことぐらいは聞いておかないといけなくないだろうか。
クリスマスの浮かれ気分は街中だけのものではない。
女性比率の高いうちの会社でも、イブの日が迫るにつれ後輩OLの浮つき具合がひどくなっていった。ロッカー室での彼女らの会話は日に日に喧しくなり、給湯室で息ぬきする回数も増えている。話題の大半はイブの晩をどう過ごすか、誰が狙い目か、それと「可哀想」な先輩OLについての、あてつけめいたひそひそ話。
的外れの噂は別に腹も立たないけれど、さも分かったような目配せや囁きの積み重ねにイライラさせられるのも事実だった。いっそ良平との関係を暴露して内輪で固まっている
「寂しい」後輩OLの鼻を明かしてやりたい衝動にさえ駆られる。
原口良平が独り身の男性として彼女らにカウントされていることは、軽い優越感と同時に小さな不安の芽となっていた。他の子に誘われてもきっぱり断るに違いないと思う一方、もしかしたら私はキープされているだけで他の女性と過ごすかもしれない、なんてあらぬ猜疑心を抱いてしまうのだ。特別にどこかでイベントというのではなく、聖夜は私の部屋で過ごしたいという彼の希望も、かすかな不安となっていた。
恋人じゃなくてSMの奴隷だから、別にロマンチックなイベントも必要ない?
下らなすぎる発想だ。でも、不安は、不安だった。
若々しくいきいきした後輩OLの姿を見ていれば、そのくらいの気持ちは抱いてしまう。
仕事を効率よくこなし彼女らを動かす私の姿は「できる」女性のようかもしれないけれど、それとてOLの範疇をこえるものではないからだ。特別な資格や能力があるわけでもない。
漫然と重ねたOL生活の慣れだけでどうにかしているだけなのだ。
クリスマスイブ、その当日。
いつものように彼とは家を出る時間をずらし、先に会社に向かう。半日もすれば仕事も終わり、プライベートな時間を満喫できるだろう。はなやぐ心を押し隠して着替えていた私は、ロッカー室の反対側で始まったOLたちの会話に思わず手を止めていた。
「じゃあ原口君も誘っちゃっていいんだよね」
「うん、OKみたい。茂木君を通してそれとなく確認したら、やっぱり今夜ヒマだって」
「いーねー。ちょっと楽しくなりそう」
聞き覚えのある後輩OLの声。となれば、原口君というのは良平の事に決まっている。
誘う、という言葉に思わず耳が尖ったものの、彼があんなキャピOLになびくはずもないと思ったから、私は先に立ち去った。
だから、お昼時のオフィスでくつろいでいた良平を彼女らがぐるっと取りかこむまで、私はその「誘い」というのが若い社員だけを集めた忘年会の誘いであることに気づかなかったのだ。
「ね、出てくれるよね?」
「だって、無理だろう。君たちもいきなりすぎるって」
気がづいた時にはもう口を出したり、タイミングよく別の用事で割って入れる状況ではなかった。かすかに眉をしかめた良平の顔に、何食わぬ顔でお弁当を広げたまま机の下で強く手をにぎりしめしまう。
要領のいい彼のこと、うまく切り抜けると信じていた。けれど。
「それとも、まさかつきあってる女性がいて、ホントは会う予定になってるとか?」
「え、そんな‥‥?」
良平がいいよどむのが分かった。ほんの一瞬、すがるかのような瞳が私に向けられる。
その視線に‥‥私は応えることができなかった。なんていって会話に割りこめばいいのか、あるいはどうしたらいいのか、分からなかったのだ。
部屋の向こう側で、良平が焦ったような取りつくろいの笑みを浮かべる。
「まさか。つき合ってる人なんて、あはは」
「だよねー。ならいいジャン。親睦を深める大切な機会なんだし。ね?」
それ以上聞いていられなかった。
立ち上がり、早足で廊下に出る。背後の部屋で小さなざわめきが起きたが、それが彼のものなのか、彼をとりまくOLたちの歓声なのか、よく、分からなかった。
意味もなく化粧室にとびこみ、誰もいない鏡に顔を映す。
なぜなんだろう。
お互いつきあっていることは会社では伏せておく。そう約束させたのは私だというのに。
鏡の中のOLはひどく傷ついた目をしていた。
いつ仕事が終わったかもよく覚えていない。
ぼんやり、淀んだ気分のまま機械的に仕事を終えた私は、自宅へ向かう電車に揺られていた。まわりにはカップルやメールで連絡をとりあう人々がめだつ。みな、幸せな聖夜を目の前にしているのだ。
なぜとなし、惨めな気分だった。
周囲に取り繕っていた良平にも。そんな彼を救ってあげられなかった自分にも。
お局OLとはいえ、私はあまり怖がられるようなタイプではなかった。それなりに指図して彼女たちを動かすことはあっても、叱責したり畏怖されたりする感じではない。その気おくれが、あんな結果を招いたのだ。
結局、彼はわざとらしい日取りの忘年会への参加を、飛び込みで承知させられたらしい。
メールで届いた謝罪には、まだ返信を打てずにいた。感情的になってしまいそうで言葉が見つからない。
闇夜に浮き上がる駅前のショッピングモールを抜け、街角の飾りつけを意識しないよう自宅に戻る。なにをする気力にもなれず、服もバッグも投げ出した私はため息をついた。
なにが年上だというんだろう。大事な時に、彼を庇ってあげられなくて。
準備しておいたクリスマスキャンドルが、綺麗にセッティングされたテーブルクロスが、ものわびしくリビングで灯しだされていた。買ってきたケーキも冷蔵庫に眠ったままだ。
独りで食べることになるかも、そう瞬間、食欲はまるでなくなっていた。
なにがいけないんだろう。
これ以上ないほど彼とはうまくいっている。なのに‥‥
知らず知らずPCを立ち上げた私はネットをのぞいていた。いくつものSM系のサイト。
そこに書かれた、ご主人様の教え。愛情なんて必要ない。カラダに刷り込ませればいい。
深いエクスタシーを知ることで女は自然と従属するようになる。それが調教だ‥‥連綿とつづく、ぞっとするような言葉の羅列。
彼の求めにさからえない私は、すでに調教されているのだろうか。
ドアノブの回る音は静かで、私は気づかなかった。
「ただいま‥‥彰子さん」
「!?」
突然の声。
ふりかえると、うなだれた表情で良平がそこにいる。
「ようやく振りきって帰って来たよ。あいつら‥‥ホント、二次会だなんだとしつこくて」
「‥‥」
「何度も連絡入れたのに、彰子さん出てくれないし。ひどいよ」
傷ついた彼の視線が私をえぐる。嬉しさと、彼を責める感情と、寂しさとおののきと。
おかえりの声が喉につっかえてうまく出てこない。
お酒の匂いと、誰とも知らぬ香水の匂いが、私の気分をおかしくさせる。
他の女の子たちと一緒に聖夜をすごして‥‥良平は‥‥
「彰子、さん?」
不平を鳴らしていた良平は、返事もせずにたちつくす私の異常に気づいたのかあわてて近づいてきた。肩をつかむ男性の手。私をだきしめ、なし崩しにうやむやにする良平の手。
その強い力が、反射的な拒否反応を起こさせる。
「待って、待ってダメ」
「どうしたの、彰子さん。なんか変だ‥‥」
言いかけた彼がふと私の背後に向かい、PCのモニターをのぞきこんでいた。
SM系の出会いサイトに書かれたコラム。
「どうして」
あっけにとられた彼の表情を見たとたん、さぁっと後悔で血の気が引いていく気がした。
見られてしまった。私の不安を、私の不信を、私の背信を。そしておそらくは、いままでずっと私が疑い続けていただろうことも。
私のために急いで帰ってきたのは、息を切らす姿を見れば分かる。本当はうれしいのだ。
だから、言いたいことがいっぱいあって、口を開いたはずなのに。
私が、私を裏切っていく。
「分からないよ、私‥‥分からないのよ‥‥良平の心が」
「えっ?」
「手軽な女だった? 私は? 調教も簡単だった?」
良平の顔がぎょっとしたように歪む。それを見て意地悪く喜んでいる醜い自分がいる。
あてつけるかのように痛烈な台詞が、こんなタイミングで一番大切な聖夜に言うべきじゃない言葉がぼろぼろあふれだす。
「おい。待てよ。待てってば、ちょっと落ち着いて」
「他の女の匂いのついた手で触らないで!」
おさえつける彼の手がいらだたしく振り払いながら、ヒステリーめいた悲鳴が口をついてとまらなくなっていた。ずっと抑えこんできた自分自身が、堰をきってなだれていく。
「SMって愛情じゃないじゃない。奴隷じゃない。そんな風に私を見ていたの。他の若い子の方が一緒にいて楽しいの。他の女の子には拒絶されるから、私を選んだの。いい年して焦っている私なんか、簡単に落とせると‥‥」
「彰子!」
不意に大声をだした良平にびくっとなった。
いつも柔らかな瞳がきり、と吊り上がる。撲たれると思った。とっさに固く目を閉じる。
唇からすべりこんだ感触は、あくまで柔らかく、暖かかった。
「ア、んふ‥‥ン‥‥りょう、へ‥‥」
私の声を、嘆きを、すべてを吸い尽くすかのように、あらあらしいディープキスが私を翻弄する。息を紡ぎ、口腔をくすぐり、交じり合う雫を強引にことほぐ。
突っ張っていた手からずるずると力が抜け、それとともに昂ぶった感情が収まっていく。
なにを当りちらしていたのだろう。彼は悪くないのだ。私に勇気がなかっただけなのだ。
今さら暴れてもしかたない。もう、なにもかも、良平に知られてしまったのだから。
「どう。落ち着いた?」
「ん」
うなずくと、意外にも彼はホッとしていつもの屈託ない笑みを見せた。
「良かった‥‥今日は悪かったね。心配、かけた」
ふわりと大きな手が背中を引き寄せ、彼の胸の中にすっぽりと包まれる。
思いがけぬ優しさに、当然の拒絶を予期していた私はどきりとした。いまだ激しく動悸を打つ胸を彼におしつけ、おそるおそるうかがうように彼の顔を下から見上げる。
「おびえたな瞳をしないでください、彰子さん」
かわいいですけどね、そういう彰子さんも‥‥冗談まじりに呟く台詞で顔が赤くなる。
「私、その‥‥」
「いいんですよ。俺だってヒス起こしたこともあったでしょう。こういうのはお互いさまですから。ただ」
「‥‥」
「そんな風に彰子さんが悩んだり苦しんでるの、全然気づかなかったのが悔しくて」
驚くほど真剣で、包容力ある男性のまなざしが私にそそがれる。
「良平」
「もっと早く言ってくれればよかったのにって、そうもいかなかったんだろうね。まさかあんなサイトの中身を鵜呑みにしてしまうほど深刻に悩んでいたなんて」
良平の声。良平の瞳。
その瞳が柔らかく細まり、囁く声はたしかに心に届いていた。
「愛してるから、心を許せるからこそ、他の誰でもない彰子さんを俺だけのものにしたいし、本当の欲望を受けとめて欲しいんだよ、俺の」
「俺自身変だと思うんですよ。けど、その‥‥性に目覚めた頃からこういう傾向があって」
「‥‥うん」
「本当に好きな女性であればあるほど、つなぎとめておきたくなるんだ。憧れている人を支配して、自分のものにしたいって。そうするとすごい欲情して‥‥はは、でもなんか、こういうの、異常だと思いますよね」
「ううん」
敬語まじりで恥じたようにしゃべる良平。耳を傾けながら、苛立ちも、不安も、混乱も、すべてがうそのように凪いでいった。
彼が吐露する心情は、多分、私と同じように彼が言いだせず苦しんでいた葛藤そのもの。
それを聞いて受け入れてあげられるのは私だけだとはっきり分かったのだ。それに首輪をつけるという特殊な行為に発情してしまうのは、私だって同じこと。
彼のおかげで、私は本当の女の悦びに、快楽の深みに目覚めたのかもしれないのだから。
「そうね、ちょっとヘンタイだけどね。私もすっかりこんな風にされちゃったし」
「えっ!? こんな風って‥‥?」
茶化して微笑みかけると、良平の返事はなぜか掠れていた。
首を傾げつつもその顔をのぞきこむ。
「キミの好みに、首輪を嵌められて感じちゃう女にされちゃっ‥‥あっ、キャァァ!」
「しょっ、彰子さん‥‥!!」
ガバッとおおいかぶさってきた良平が、それこそ無我夢中で私を求めてくる。やみくもにキスの雨を降らされ、あらゆる服の合わせ目から入り込んできた手であらがう間もなく裸身を愛撫されて‥‥
「彰子が年に似合わず可愛いコトいうから、俺、もうこんなに」
「似合わずは余計よ! あ、ぅンっ‥‥」
こんなに、の先は口にせずとも分かっていた。私のお尻におしつけられ、痛いぐらいにスーツの下で腫れあがって反り返っていく男性のこわばり。そのぬくもりと脈動まで生地ごしに感じとれるようで、半ば脱がされかけた格好のままドキドキしてしまう。
彼に求められている。そして、もちろん、私も‥‥
いつかしなだれて彼の指づかいに甘い息を吐いていると、良平がそっと何か差し出した。
いや、なにか、ではない。分かっている。分かりすぎている。私のスイッチ。
「彰子‥‥ね、分かるだろう?」
「んンン」
鼻から抜ける喘ぎをこぼし、かろうじて最後の理性で抵抗をこころみてみる。
「でも、食事は? ケーキは? プレゼントは?」
「全部あとまわし」
「そんなぁ‥‥ムードが、だって」
「だって、食事よりシャンパンより‥‥俺は彰子を味わいたいんだ」
直撃、だった。
こんなクサイ、青くさい気障なセリフに、胸の中をわしづかみにされてしまうなんて。
若さと魅力に訴えかけた猪突猛進のアタック。最初のデートの時も、こんな風にぐいぐい押し切られて、それがまた嬉しかったっけ‥‥
つかのま唇を引き結び、覚悟を決めてふりかえる。期待に満ちた良平を見つめ返して。
それでも語尾は消え入るように恥ずかしくなり、視線が伏せ気味になってしまう。
「良平‥‥おねがい」
「うん」
「首輪を‥‥嵌めて欲しいの。私を、繋ぎとめて。良平のモノにして」
良平の若さに感化されたのか。私が口にしたのもまた、甘すぎる淫靡なセリフだった。
それは、あまりにはずかしいおねだり。
セックスして、メチャクチャにして、そう素面で言っているようなものだから。
獰悪な獣のようにぎらつく雄の視線にたえきれず、まぶたを閉じ、後れ髪を梳きあげておとがいを上げた私は、革の吸いつく感触を、かちりと施錠され外せなくなった南京錠の軋みを、ただ感じていた‥‥‥‥
☆
甘い悦びと奔流が、私の中でぐちゃぐちゃにうねり狂っている。
首輪を嵌められた私は、さらに首輪から伸びた金具にペットを散歩させるためのリードまでつながれ、その端を彼に握られた姿でPCのデスクに手をつかされていた。
命令されるがまま大きく広げた下半身がふるふると波打っている。
しゃがみこんだ良平はねちっこくいやらしく下半身を愛撫していた。じわじわ指の腹を這わせ、物欲しげなショーツのまわりを避けながらお尻のラインを揉みこみ、たぎりだす下腹部のデルタ地帯にはあえて触れずに周囲から責めあげてくる。
「動いたらダメだよ、彰子」
「んッ‥‥はい」
従順な声音にまじる翳りは、火照るだけ火照らされてお預けにされるカラダの恨めしさ。
じわじわ炙られていくのに、あと少しで快楽の波涛に届かない。圧倒的なものたりなさと切なさが、薄れゆく快楽に無意識にしがみつかせてしまう。惨めなその疚しさときたら。
ショーツのクロッチなんて恥ずかしい位ジュクジュクに湿り、うねりたぎった女の帳から涎と雫をべそべそに吐きだしているのだ。
乱れてしまうのが恥ずかしい。彼に見られると意識が飛びそうなほどの羞恥をおぼえる。
ホントは、もっと乱れて、めちゃくちゃに悶えたい‥‥けれどそれは、私自身が普通の女じゃなくマゾなんだと、特殊で変なのだと認めさせられるようで、すごく、悔しいのだ。
そんな時に限って心を読んだように良平が私をからかう。
「嫌なんじゃなかったの、首輪で感じさせられるの? すごいよ、彰子のココ」
「‥‥‥‥い、意地悪‥‥」
ハスキーに裏返った吐息さえもが、バラバラに寸断されていく。
不審と疑いの証拠であるSMサイトのページを表示したまま、深い愛情に裏打ちされたペッティングを施されていく恍惚は、まさに良平の与えた甘い罰だった。
惚け、とろけて、めくるめく情欲が、モニタに映りこんで婉然と微笑み返してくる。猫の首輪そのままに喉からぶらさがった南京錠が揺れていて、否応なく所有され支配されて
いる現実を、被虐的な女の裸身をまざまざと意識させてしまう。会社帰りのスーツのまま、胸元からおへその下まではだけられている自分が信じられない。
残骸めいて肘にからむジャケットに腕をとられ、彼を抱き返すことも満足にできずに。
首輪によって完全に支配された私は良平のモノ。惨めな姿も恥ずかしい吐息も、すべて彼だけのモノ‥‥
前触れもなくつぷんと、しどどにあふれかえった蜜壷に人差し指で掻き回された。
じゅるりと舌なめずりするかのような卑猥な水音。
くぅっと体躯が反り返ってしまい、あわてて肩に鼻先を押しつけてよがり声をかみ殺す。
「ン、んふぁ‥‥ァ」
「やっぱり、彰子も不安なのかい? こうして感じてしまうことが」
「だ、だぁって‥‥」
抗議の声はもはや拗ねた少女の駄々にしか聞こえない。年甲斐もない、はしたない仕草。
普通に恋して、普通に結婚して、そう夢見ていた自分とはあまりに真逆のありようなのだ。
ニッと笑う気配に胸がドクンと跳ね上がる。
何をされちゃうんだろう‥‥良平に、どんな意地悪をされちゃうんだろう‥‥
不安におののく理性と、もっと堕とされたくてうるんだ裸身とが、私の中でせめぎあう。
心憎いばかりの手管で乳房をキュキュッとしごきながら、彼の手がキーボードで踊った。
不意に画面が切り替わる。
『ころになでおなにな生活』
~メスネコはやっぱりエロが好き!~
(えっ‥‥!?)
映しだされたサイト名に息をのんだ。柔らかいタイトルにはどこか淫靡な響きが秘められていて、変にドキリとさせられる。プロフィール欄には本人とおぼしき女性の写真。耳からうなじにかけて顔を隠しつつ撮った横顔の輪郭に色気があって見入ってしまう。
「例えば、そう、このブログなんか君ごのみだ」
「‥‥!?」
ひそやかな吐息とともに耳たぶを甘噛みされ、こりこりいじられて背筋がつっぱった。
思わず引けた腰が彼の膨らんだ下腹部に押し付けられ、いやらしく火照った顔をモニタに向けさせられた。自然、うつろな瞳に文章が飛び込んでくる。
2004年06月14日
とうとうやってしまった…露出
ベランダに全裸で出てしまいました…
正確に言うと股縄だけつけて。
(!?)
瞬間、瞳が大きくなり、私は動揺してしまっていた。
なにを言っているのだろう。このブログは。ベランダに‥‥はだか? 全裸? なぜ?
気を取り直すまも与えられず、背後から抱きすくめる手に裸身を嬲られ、煽り立てられて前のめりにカラダが傾いだ。首輪を引かれ、喘ぎながら続きを強制的に読まされるのだ。
夜風が心地いい…全身が火照っているから。
体がふらつきそうで冊に片手をついて右手で股縄を引っ張ったり、クリに当たっている結び目を押しつけたり、二重になっている紐をこじ開けて指を中に押し込んだり…手近にある洗濯ばさみは当然のように乳首に…
「ひゃぁア!」
ギリッ‥‥尖った乳首をミシミシッと左右同時にひねり上げられ、喉から悲鳴まじりの嬌声がこぼれた。本当に、私自身が洗濯バサミで虐められているみたいに。それほどに、われを忘れて扇情的なブログの中身に魅入ってしまったのだ。
震える半裸の躯が、良平の腕の中でのたうっていた。
慰撫され、昂ぶらされた私の裸身は、わけもなくブログの文面にシンクロしていく。
「君と同じで、いやらしい欲望に思い悩むOLのブログなのさ、彰子」
「!?」
ドクンと脈が乱れる。まるで、動揺した私の心のうちを見透かされでもしたかのように。
私と同じ‥‥じゃあ、この作者も‥‥ヘンタイ的な、女の欲情におぼれて‥‥違う、でも私はそんな露出なんて恥ずかしいこと‥‥
「露出とSMじゃ——首輪好きじゃ——違うと思うかい?」
「‥‥!」
「どっちだって、普通は人に言えない恥ずかしい性癖だろう?」
目を見開くのと同時につまはじく手で乳首をこねまわされる。円を描いてくすぐる絶妙なタッチに、きゅうんと奥深い快楽が子宮の底からわきあがった。膝がガクガクし、机の天板をつかむ手が白くなるほど指に力が入ってしまう。
「ん、ぁぁァ、ダメ、見たくない」
「何言ってるの。ほら、もっと読んでみて。目をそらしたら‥‥そうだね、オシオキだよ」
「やぁッ、嫌ァァ」
『お仕置き』などという得体も知れない響きに敏感に感応した裸身がどろどろになり、つるんと太股まで剥きおろされたショーツとデルタとの谷間にしたたる銀のアーチを描く。
首輪を引っぱられれば、のけぞる私に顔をそらす自由はない。
切り替わる画面と彼の手管が一体となり、私自身がおそれていた暗い心の淀みを、顔をそむけつづけていた真実の被虐癖を私の中から引きだしていく。
ひとつ言えるのは、「露出」がしたかったわけじゃないと言うこと。
「露出」は「恥ずかしい目に遭いたい」ためにしてる…ってことだと思います。
だから、ずーっと遡って、罪悪感を感じながらオナニーをしていた頃から、そういう欲望を持っていたんだと思います、無意識のうちに…
私はオナニーなんて恥ずかしい事をしてしまってる…
恥ずかしいと分かってるのに気持ちよくて止められない…
こんなことしてるなんて誰かにばれたらどうしよう…
官能に溺れながら、糾弾されているかのような恥ずかしさと疚しさ。意地の悪い良平の囁きと入念に私の弱点を知り尽くしたペッテイングが、理性をもうろうとさせていく。
「はァン、んぁ、やめよう‥‥よう?」
「どうして」
追い上げられた私は半泣きの表情のままうわ言のように否定ばかりくりかえし、かってないほど発情してしまった裸身に、わきあがる淫靡な情欲にあらがっていた。
うそ。信じられない。こんな匿名のブログ、ただ煽っているだけ‥‥
そう思いたいのに、なまなましい記述はただただリアルで、目が引き寄せられてしまう。
明らかにホンモノの、真実の告白。嘘でない証拠に、私はこんなにも動揺しているのだ。
首輪と露出。行為は違うけど、でも、そこには確実に同じ罪悪感めいたものがあって‥‥
自分が普通じゃなくなっていくのが、怖い。
気持ち、よくて‥‥
首輪をされることでモノのように扱われるのが、自尊心をつき崩されるのが、快感で。
だから、6つも下の良平にやすやすと煽られてしまうのが悔しくて、感じてしまって‥‥
乱れた私を嬲りながら、良平が次々と続きを見せていく。
2004年06月20日
プライドをずたずたにして!
人として、女性として、OLとして、上司として、先輩として…意識してなくてもけっこう色々ありますよね、プライドって。
なくては困るけど、あり過ぎるのも困る…それがプライドだと思います。
マゾなんだから、プライドなんかないだろう?
トンでもありませんね。むしろ、プライドが高いからマゾ…なんじゃないかなと思います。
そのプライドをずたずたにされることに快感を覚えちゃう…んです(恥)
たまらなかった‥‥あまりにもシンクロしすぎる文面の一字一句が。
灼りついたカラダをまさぐられ、濡れた下腹部をつぷつぷ指で弄られながらの愛の囁きだなんて。うるんだ流し目で振り返り、彼の首をぎゅっと引き寄せて唇を重ねてしまう。
口腔を焦らされ、くすぐられ、名残惜しげな私の中から舌が引き抜かれる。
「あ、ふ‥‥」
したたる涎のアーチ。官能に溺れた私を告発するかのように糸を引いて。
「彰子さんが怖がっているのを知って、まず、このブログのことが思い浮かんだんだ」
「私と、このブログの作者、と‥‥?」
「そうだよ。例えば、このエントリなんか、どう」
もういいから、今は、ただ良平に溺れたい‥‥
下腹部をもどかしく擦りつけて挑発しても、彼は笑って私を焦らすばかり。唇と唇とをふれあわせて小鳥のようについばみながら、そっとおとがいをつつままれて画面へと誘導されていく。
2004年07月24日
バッドエンド
今夜は吐き出させてください…
今日はこんな事まで考えてました…
彼は私に愛情などカケラも持っていない。
私に近づいたのは、使い捨てのM女が欲しかっただけ…
もちろん、彼は私がメスネコであることを最初から知っていて、私がどこでいつ変態的オナニーをしていたかも熟知している。
そして、ある日彼は突然牙を剥く。
剥き身のお尻に押し付けられていた彼の下半身の感触。それがいつのまにか高々と反り返って雄々しい脈動とともに人肌のぬくもりがじかに感じとられる。上着はそのままに、下は私と同じすっ裸なのだ。
その意味することに気づいた途端、おののきでカラダがひきつりそうになった。
耳の奥まで血管が沸騰する。
この状態で、男女のすることなんて、一つきり‥‥
「‥‥こんな、風に。なんてどう?」
「えっ、りょう‥‥へい?」
声をかすれさせて呟く良平が、手元のリードをくんと引っぱった。
あっと声をあげ、よろめいたカラダを首輪一つで自在にコントロールされるいやらしさ。
頭を押さえつけられ、テーブルに顔を押さえつけられる。モノ扱いされる惨めさに被虐の血がかぁっとたぎり、天板に鼻先をすりつけながら、ゾクゾクと浅ましい期待がわきあがってしまうのだ。
「あっ、アッ、ヤダぁぁぁッ」
「行くぞ」
耳慣れた、そして、ぞっとするほどの獣性を秘めた男の声。まるで、そう、エントリの妄想そのままに、私の気持ちなんか無視してまるで奴隷を扱うような仕草で。
こんな猥褻な文章を読みながら犯される‥‥彼の思い通りに虐められ、犯されてしまう。
そう、それこそ、ずっとするほど甘美な、もっとも恐れている幻想そのままに。
中断させようと、必死になって頭を押さえる掌の下から逃れようと‥‥
ぬちり。
灼けた鋼鉄のような感触があそこの帳をこじあけてあてがわれたのは、この瞬間だった。
思わずおびえた瞳をふりむける‥‥そこには、ニヤリと笑う彼の姿が。
「すごいじゃないか。触れただけで呑み込まれそうだよ、ココ」
「いや、嫌‥‥イヤァァァァ」
「ウソをつけよ。カラダはそうは言ってない」
いやらしいAVのように。卑猥な官能小説の筋立てのように。女の理性を剥ぎ取られて。
ウソ、ウソでしょう‥‥
こんなまるでレイプみたいに乱暴な形でされるなんて、私は‥‥
自分を見失い、おびえて彼の体を跳ねのけようとする私の悲鳴と、ほとんど同時に。
深々と、彼のたぎりきった怒張が、暴虐にあそこへとねじりこまれてきた。
ものすごい甘美な水音と、つきあげる快楽そのままに。
「‥‥ぅぐぅッ」
唇をかみしめ、必死の思いで机にしがみつく。
背後から、待ち焦がれていた彼自身に完全に貫かれ、犯されて。
信じられない。どうして感じているの。どうして流されているの、私のカラダは。
なぜ、なぜ、なぜ‥‥こんな、気を失いそうなほど、気持ちイイ‥‥!?
なんで嬉しげに腰が弾んでしまって、キリキリと彼の肉を迎え入れ、むさぼってしまうの。高々と自分から、腰をつきあげて犯されやすい姿勢をとってまで。
爪先だった足がふるふる震え、それに反して全身がびりびりと甘くしびれて崩れていく。
いつものように優しいセックスを期待していた私に…
ありとあらゆる方法で私は責め苛まれ、それでも彼にされているのだからと…何度も逝ってしまう…
数えきれないほど絶頂を迎えて息も絶え絶えのまま、なおも拘束されたままの私を残して、彼はパソコンに向かっている。
「何をしているの?」
私の声に彼が冷たく答える。
「今、撮った写真を全部掲示板にあげようと思ってね。」
自分で妄想してて怖いです…orz
「はぁァン、アァァァン」
信じられない。私、彼にレイプされてるのだ。なし崩しに、ムリヤリに。
虐められ、モノのようにあしらわれて。
声も、カラダも、意識も、なにもかもがまるでコントロールできない。パァンパァンと荒々しくたぎる怒張で突かれ、抉られ、かきみだされて‥‥その感触をむさぼるかの如く爛れきったアソコが貪欲に彼を咥えこんで離さないのだ。
キュウキュウと絡みつき、絞りあげ、ずるずると男を噛みしめて蠕動を繰りかし‥‥
あふれかえる雫が、跳ねとんで太ももどころか床まで汚し、内股をだらだらつたっていく蜜の筋が、思いと裏腹に私をくるおしく駆りたてていく。
虐められて、奴隷のように首輪で従えられて‥‥
「い‥‥イイ‥‥すごい‥‥ァァ」
とどめようのない浅ましい科白。何のことはない。ブログの作者のことなんか何も言えやしない。私の方がずっとエッチで、ずっと愛欲に溺れて、首輪になんかつながれている牝猫そのもの。お尻まで振りたてて良平を咥えこんでいるんだから。
いやらしい、それでいて残酷なブログのバッドエンド妄想をむさぼるように読みながら、あまりにもはしたないことに、私は今までで一番下腹部をあふれさせ、うるおった本気の愛液でビショビショに彼の足までも汚しているのだ。
レイプ願望めいた妄想を読みながら犯されていく現実。そらおそろしいシンクロ感が、さらに興奮とわななきを高めていく。汚辱めいた気分さえもが意識を昂ぶらせ、身も心も彼にしがみつかせてしまう。
カラダを抱きすくめる彼の腕に体重を預けて、ひたすらに腰をグラインドさせてしまう。
それでも。
「彰子、ン、いいぞ、すごい締めつけだ‥‥」
「イヤァ‥‥ひどい、こんなの」
愛情だって感じているはずなのに、彼の行為の真意がわからず、視界がぐにゃりと歪む。
わざわざこんなブログを読ませて、私をどうしたいんだろう。この文章みたく私を本当の奴隷にしたいのだろうか‥‥
涙まじりの顔をつかんで乱暴に唇を吸われる。なすがままに唾液をのまされる。
抵抗しようとは思わない。好きなんだから。溺れているんだから。
ねぇ、どうして‥‥?
「分かるかい。今の自分の感情が。状況が。ジレンマが」
「わ‥‥分からないわよ‥‥バカ‥‥」
ぐずりながら身をゆだねる私をいとおしむように、彼が動きを止めた。
「こういうことだよ」
2004年07月13日
ココロとカラダ 理性と欲情
どうしてこんなに葛藤するんでしょうね。
好きだと思えば思うほど、「したい」と思う気持ちを抑圧する自分がいます。
表面的に発情はしてないけど、一皮剥いたら欲情のマグマがドロドロ…って感じ?(汗)
自分で自分をどうコントロールしていいのか分からないんですよね。
このまま抑えていればいいのか…特に彼に対してね。
首輪を嵌められたうなじがチリチリと疼きだす。
「このブログはね、ちょうど、俺たちの関係の裏返しなんだ」
「うらが‥‥え、し?」
この気持ち、この困惑‥‥
作者の思いが痛いほどに分かるからこそ、それが私たちの裏返しというのなら‥‥
ふりむく間近に、彼の真剣なまなざしがあった。つかのまの休息。みっしり暴れくるう彼の分身に根元まで串刺しになったまま、ガクガクする足で床をふみしめ、彼にしなだれかかる。おそるおそるの、上目づかいの視線をじっと見つめ返す凛々しい瞳の底に、見た。
さまざまな打算や喜びや愛情に交じって、たしかに同じ不安の質があるのを。
「じゃあ、良平‥‥も」
「そうだよ。俺だってそうさ。本当の性癖を見せるのは恥ずかしかった。拒絶されるかも、そう思うと怖かいさ。だからこそ彰子さんの反応が本当に嬉しくて、いとおしくて‥‥」
「良平‥‥」
「だから彰子さんは絶対に手放したくない。俺だけのものにして、俺だけの‥‥」
「ふぁァァ」
ぐいっと彼が腰をつきだし、弾みでギシリと彼を喰い締めたまま、下腹部の疼きに喘ぐ。
たまらない充足感にのどをならす私の頭をおさえつけ、首輪のリードを握って、彼が再びじわじわとリズミカルに抽送をはじめだすのだ。
「もっと乱れていいんだ。俺の前では。彰子の前で、俺がありのままなのと同じように」
またも別のエントリを動かし、見せつけながら彼が動きを早めていく。
一時静まりだしていた快楽の焔が、またたくまに大きな息吹となり燃えさかっていく。
のしかかられ、屈辱的な体勢で、立ったまま背後から獣のように押さえつけられ、爛れきった媚肉を穿ち抉られて、必死になって机にしがみつく手を支えに激しい律動を受け止めようとする。
2004年12月21日
明るいSM?
妄想の中のSMには明るいところなんてどこにもない。
じゃあ、彼としちゃったのはどうかと言うと…
少なくとも妄想の中の登場人物のようには酷い事はされない。
それはなぜかと言うと…私の彼の関係が恋人(婚約者)だから…じゃないかな?
彼とした時も、お互いに役者ではないから、多少優しい感じじゃないと演じきれない、いきなり「ご主人さま」とか「このメスネコが!」なんて事は言えないから、「ごっこ」の部分で止まっているんじゃないかな?
婚約‥‥者‥‥!?
ほんの一瞬、琴線に触れた言葉が、あっという間に意識をかすめて吹き飛んでいく。
こんな風に赤裸々な感情を持って、恥ずかしいながらも性癖を打ち明けて、それで、彼と秘密を共有したまま、結婚することができるなんて‥‥
嫉妬にも憧憬にも似たそんな思いさえ、悠々と抜き差しをくりかえし、抜かりなく乳房に、太ももに、ワレメの尖った肉芽にと指を這わされては、覚えていられるはずもない。
ビリビリした電撃が裸身をすみずみまでかけめぐり、ズンと突き上げられるたびに深くみたされきった情欲の波がのしかかってくる。腰をあわせ、ずるりととば口まで引き抜かれて焦らされ、長いストロークでよがらされながらうなじを舐め上げる舌のざらつき具合に頭を真っ白にさせて海老ぞりになってしまう。
テーブルにしがみついてうねり乱れる快楽をやりすごそうとする‥‥その爛れた裸身をぐいと引き起こされ、いつかのように左右の手首をがっちり握りしめられた。ほどけない男の力でホールドされた両手は手錠でも嵌められたように動かせない。そのままカラダの後ろに手を引っ張られ、不安定な状態で上半身を吊られたようになってしまうのだ。
何もかもが彼まかせの、自由にならない奴隷の状態。
「やっ、イヤ‥‥このカッコでされるのは、イヤァァ‥‥」
「いいんだ‥‥怖がらず、本気で感じても‥‥」
苦しげに息を切らし、かすれさせながら、彼が私を大きくシェイクする要領で蜜壷の中をかきまわしてゆく。自発的ではなく受動的に。人としてでなく獣のように。それで彼が悦ぶのなら、私も、たぶん、もう怖くない‥‥良平を受け入れつつ、バラバラの、とぎれとぎれの思考の隅でそんなことを思う。
快楽に寸断され、なにもかも、私を責め立てる彼との交わり以外のすべてが溶けていく。
パァンパァンと音立ててぶつかりあう肉と肉のきしみ。
深いストロークにたまらずあそこを収縮させ、逃すまいと彼をひきつけて絡みつこうと蠕動をくりかえす粘膜が、激しい抽送でひくひくとめくれあがっていく。 喘ぎ、吐息、汗だくになってからまりあう肢体。首輪を引かれ、挿入された猛り狂う脈動がひたすらにいとおしくて。
ズクズクに溶けた秘裂を拡じあけたまま、卑猥な汁をしたたらせ打ち込まれる律動‥‥
分かっている。分かるのだ。ずっと前から、初めてカラダを重ね、初めて首輪に狂ったあの夜から、良平の愛情くらい、優しさといたわりぐらい、ずっと分かっていたのだ‥‥
だって、口でなにを言うよりも深く、彼の感触は私自身の裸身に刻まれているのだから。
両腕をつかまれ、後ろ手にひっぱられ、それこそ、轡を噛まされた野生の牝馬のように。
「‥‥ッ、はぁッ‥‥ンァ、っっぁぁァン!!」
官能という昏い大海の水面下に引きずり込まれ、溺れるものの性で必死に息継ぎをする裸身が、汗みずくでのたうちまわっている。自分の中からわきあがる快楽さえ、コントロールする自由を奪い取られ、いまはただ底知れぬアクメの深みにおののきながら、すべて彼のなすがままに追い上げられ、載せあげられ、乳房を揺すりたてて連鎖的にイかされて
しまうほかない。
首輪の持ち主・飼い主にペットのように躾けられ操られて、なにもかも不自由な奴隷の身分のままひたすらに責めあげられ、何度も腰を突き入れられて喘ぎ、口の端から涎すらこぼしつつ、めくるめく交合の頂点へ、奴隷のエクスタシーへと、いきおいよく突き上げられてゆく。
恋人である限りは、「凌辱」だの「屈辱」だのっていうのは無理だと思う(笑)
だってラブラブなんだもん(爆)そこまでの演技は難しいですよね。
できるは…羞恥と露出くらいまで…かな?
知っているんだから。そんなこと、とっくの昔に‥‥
深々と繋がったままの小刻みな抽送そのものが、みだらにうなじを這う彼の舌が、画面の向こうで照れたようにセックスについて語るメスネコさんの言の葉にシンクロしていく。
羞じらいつつも赤裸々な内心をつづり、変態めいた性癖にとまどいつつも画面の向こうで悶え悩乱する女性のイメージが、結婚相手に責められて悦んでいるその愉悦が、モニタのこちらで一体となって貫かれ、ひくつくねばる粘膜をえぐり掻きまわされる私自身に完全にかぶさっていく。
ジュブジュブとわきあがる淫汁のこだまが、いっそう高く熱いしぶきをほとばしらせて。
モニタに反射する痴呆めいた瞳に、しっかりと見つめ返されて‥‥
「ンァ‥‥イ、イィィ‥‥‥‥ッッ」
「しょ‥‥う‥‥こ!」
ひたすらに追い立てられて絶頂の悦びさえ声にできぬほどの瞬きと恍惚の刹那、躯の芯めがけた熱いしぶきが、攪拌された白濁が濁流そのままに叩きつけられる。一瞬ふわっと足から浮き上がるような浮遊感、それで十分。最後の枷を踏み越え、現実と理性の波浪を踏み外した私は私自身さえ認識しきれぬまま、なだれを打って真っ白に染まった虚無へと、
めくるめく奈落のあぎとへと滑落していくのだ。
終わりのない絶頂、とどまるところのない落下‥‥
深すぎる魔楽の余韻はいくたびとなく私を襲い返し、良平の腕に捕らわれたまま裸身がヒクヒク自立的に痙攣して止められない。壊れた人形のように男性の腕に支えられ、未だつながったままの肉の実感を痛いほどに噛みしめながら、なかば意識もない私はようやく、遠い意識をじわじわと手放していった。
☆
交錯するのは、荒い吐息と焦点のさだまらない瞳ばかり。
ふたたび浮上した時、私たちはベットの中にいた。たくましく細身の体躯が、いつもと変わらぬ誠実さで私を包んでいた。情事の後のみちたりたけだるさが、太い腕の中で私をのびやかに解放してくれている。
首に伸ばした手が金属にふれ、無意識に私は安心していた。
「おいおい、どうしたんだい」
「ううん。なんでもない」
私の首に嵌められたまま。つながれたままの首輪とリード。彼にしっかり繋ぎとめられているこの現実に、身も心も彼にそそがれているこの現実に、深い充足感をおぼえる。
私は彼だけのもの。
そして、彼だって、私だけのものなのだ。
「ところで、これ。その、さ、シャワーを浴びて食事する前に‥‥メリークリスマス」
「これ、ひょっとして‥‥?」
目を見開く私に、彼は黙って微笑んだ。
彼が渡してくれたプレゼント包みからできたのは、きらりと輝く指輪だった。ダイアをあしらった、かなり高価なものだ。おそるおそる指に嵌めてみるとサイズまでぴったりだ。
「いつのまに、私のサイズを」
「それを調べてのけるのが、男の甲斐性ってもんじゃないかな」
睦言めいて耳たぶの裏から囁かれる。まだ胎内をかけめぐる歓喜の息吹にふっと熱い焔を送りこまれ、イったばかりの躯がぞくぞくと疼きだす。
なにもかもがピタリと枠にはまった‥‥そんな気が、ふと、した。
わざわざあのブログを見せ、ああいう話をして、その後にこのプレゼント。偶然だとは思えなかった。少なくともこれが彼の解答なのだと、そう誠実に信じてもいいのではないだろうか。瞳を奪う輝きを何度かかざし、改めて思う。
「あ‥‥プレゼント、私、私もあるの、ちょっと待ってて良平」
「ダメ」
起き上がろうとしたカラダをぎゅっと抱きすくめ、彼が言った。
「今は、彰子さんの本音が聞けただけで嬉しいから。なにより。こうしていたいんだ」
「本当を言えば、ね」
「うん?」
「俺の欲望は、もっと深いんだ。いつか彰子さんにも知ってもらいたいと思う」
おや、と首をかしげて見つめ返す。彼の瞳はきらきらしていた。いたずら好きの少年のように。ふと嗜虐心にかられ、わざと怖い顔を作って彼をにらみつける。
「さっきみたいのはもう嫌だからね。あんな怖い妄想を見せつけながらムリヤリのエッチだなんて。どうしてあんなことするの」
「‥‥うん、その」
良平は、少し恥ずかしそうに目を伏せ、歯をのぞかせて笑った。
「好きな女性にちょっとイジワルしてみたい‥‥そう思わない男なんていないよ」
「‥‥‥‥‥‥ふぅん」
舌の先で十分にその内容を転がし、吟味して、やがて納得する。ま、いいか。この辺で許してあげてもいいかもしれない、と。
「ひょっとしたら‥‥さっきの比じゃないかもしれないよ」
「うん?」
「俺の、深い欲望って。彰子さんに、どう思われるか」
そう語る彼の底には、やはり同じ‥‥共感への期待と、引かれることへの不安が。
年上の私がリードし、時にリードされていくいやらしい関係。その深すぎる深奥に眩暈さえおぼえつつ、恥ずかしさに熱くなる頬を意識しまいと私は流し目で彼に囁いた。
「いいわ。その時は、うん、私に‥‥逆らえない快楽を、ちょうだいね」